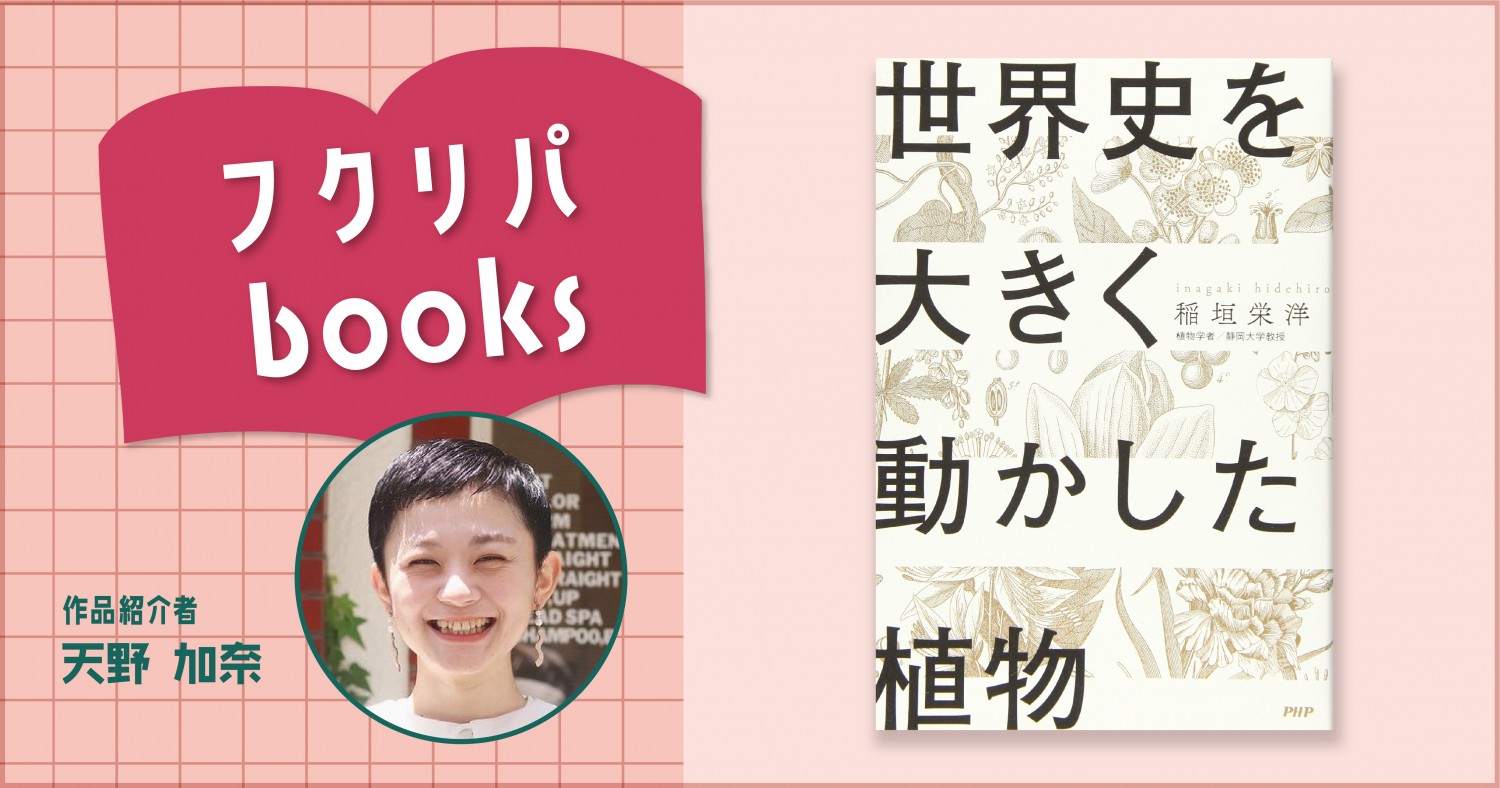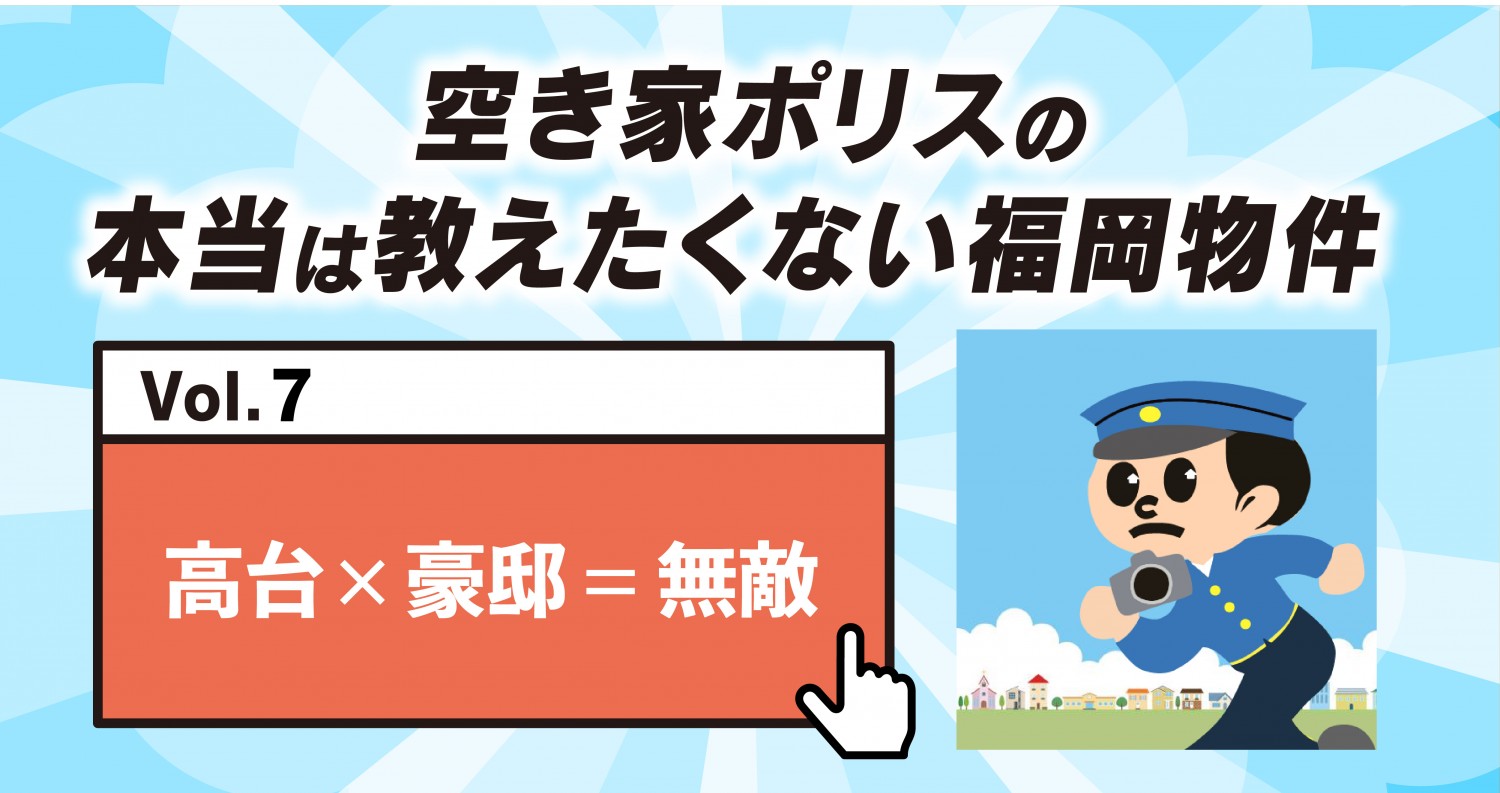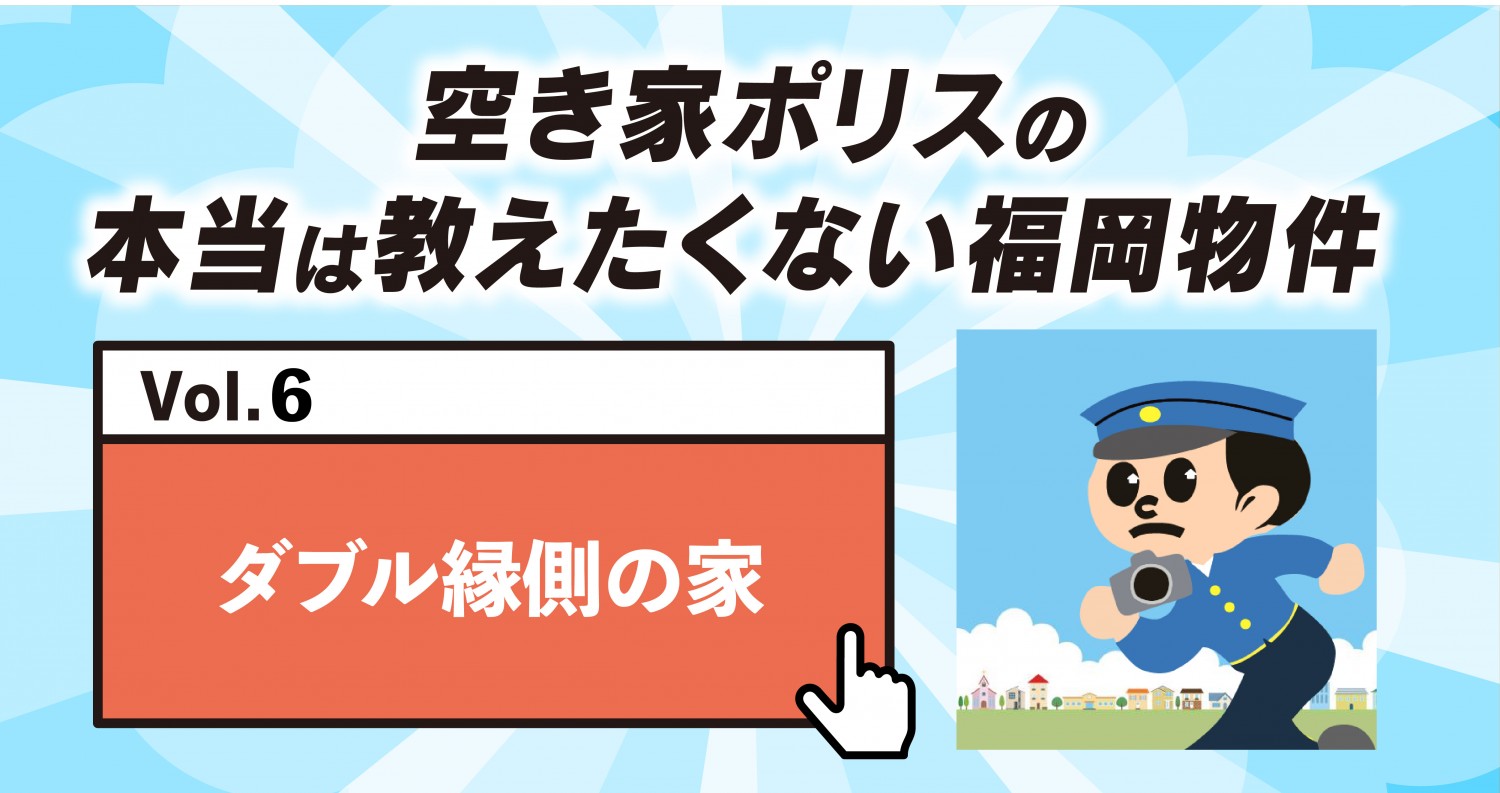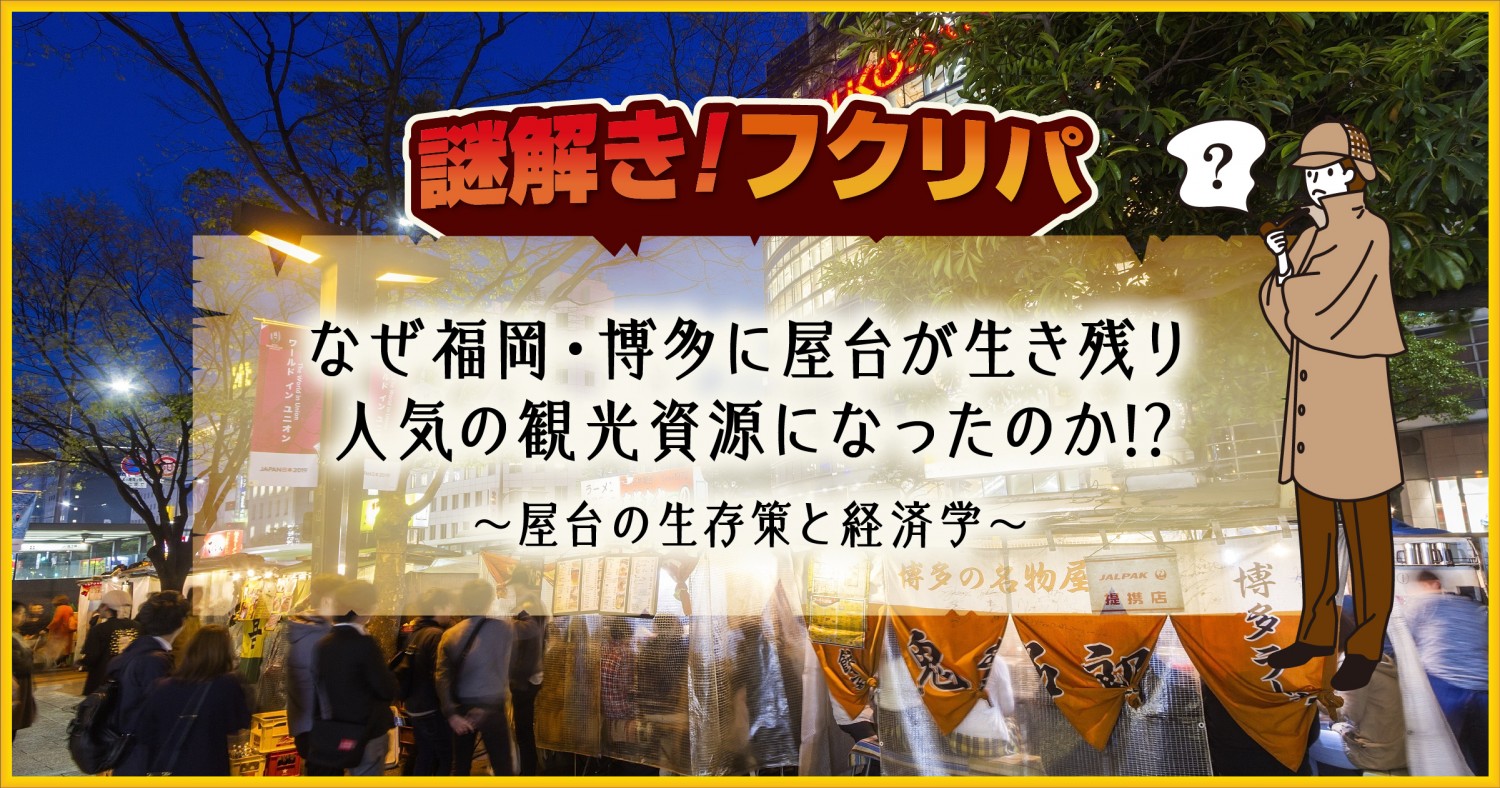- #まちと暮らし
博多駅前にアートな仮囲いが登場!108 ART PROJECT
「108 ART PROJECT」という取り組みをご存じでしょうか?アートの力で、まちの景観を豊かにし賑わいのある街づくりに貢献することを目的に2021年に発足されました。全国で取り組みをされており、今回福岡でも展開されることに。福岡市地下鉄七隈線全線開通の仮囲いに描かれる作品やアーティストについてご紹介します。
イネ科に思いを馳せないか?麦畑を見て思う、進化のいたちごっこ|『世界史を大きく動かした植物』稲垣栄洋
自分をリープアップしてくれる本を、ライター目線で1冊ずつ紹介する「フクリパbooks」。前回は仏教×鬼滅の刃をキーに本を紹介してくれた株式会社ダイスプロジェクトのプランナー・天野加奈さんが、麦が育つ&お花見のこの時期におすすめの一冊を選んでくれました。
舞鶴公園でキャンプ!3年ぶりに開催「FUKUOKA MACHI CAMP PARTY 2022」とおすすめキャンプ情報
福岡市中央区の舞鶴公園で、1泊2⽇のキャンプができるイベント「FUKUOKA MACHI CAMP PARTY 」が開催されます。
本当は教えたくない福岡の空き家物件『「高台×豪邸=無敵」の家』
「空き家ポリスの本当は教えたくない福岡物件」。「住む予定もないのに、おもしろそうな物件を探して見に行く」ことを趣味とする空き家マニアが、福岡の空き家物件を紹介していきます。 第7回は、「高台×豪邸=無敵」です。
暮らしにプラスフラワーを!「お花のある暮らし」の作り方
3月になり花と触れ合う機会も増えてきたのではないでしょうか。 前回#19の記事では「ロスフラワー問題」についてと、花の廃棄を減らすアイデアをお話ししました。 花の出荷数が全国3位の福岡から、花の廃棄を減らし、もっと身近に花を添えることを目指し、今回はもう少し踏み込みます。 コミュニケーションを増やし、つながりをつくることにもつながる「お花のあるくらし」、その実現に向けたアイデアについて触れていきます。
本当は教えたくない福岡の空き家物件『「ダブル縁側」の家』
「空き家ポリスの本当は教えたくない福岡物件」。「住む予定もないのに、おもしろそうな物件を探して見に行く」ことを趣味とする空き家マニアが、福岡の空き家物件を紹介していきます。 第6回は、ダブル縁側の家です。
バス停とともに記録を残す「西新パレス前」
一見なんてことないバス停とそのまわりも、視点を変えれば観光資源。そんな思いで福岡市のバス停を取り上げ、ご紹介する本企画。 連載6回目は3月末でボウリング場とホールが閉鎖してしまう「西新パレス」のバス停から出発します。
福岡への移住を考えている方必見!福岡の住みやすさやおすすめのスポット、働き方まで
春の足音を感じる季節。4月から新生活をスタートさせる方も多いのではないでしょうか。新生活といえば、かつては進学や就職がほとんどでしたが、最近は4月に合わせて“移住”するという方も増えています。福岡も住みやすさはもちろんのこと、移住者に対する支援などが充実していることから、年々移住者が増えて続けています。福岡に移住する方、そして移住を考えている方にぜひ読んでいただきたい、フクリパ記事を厳選してみました。