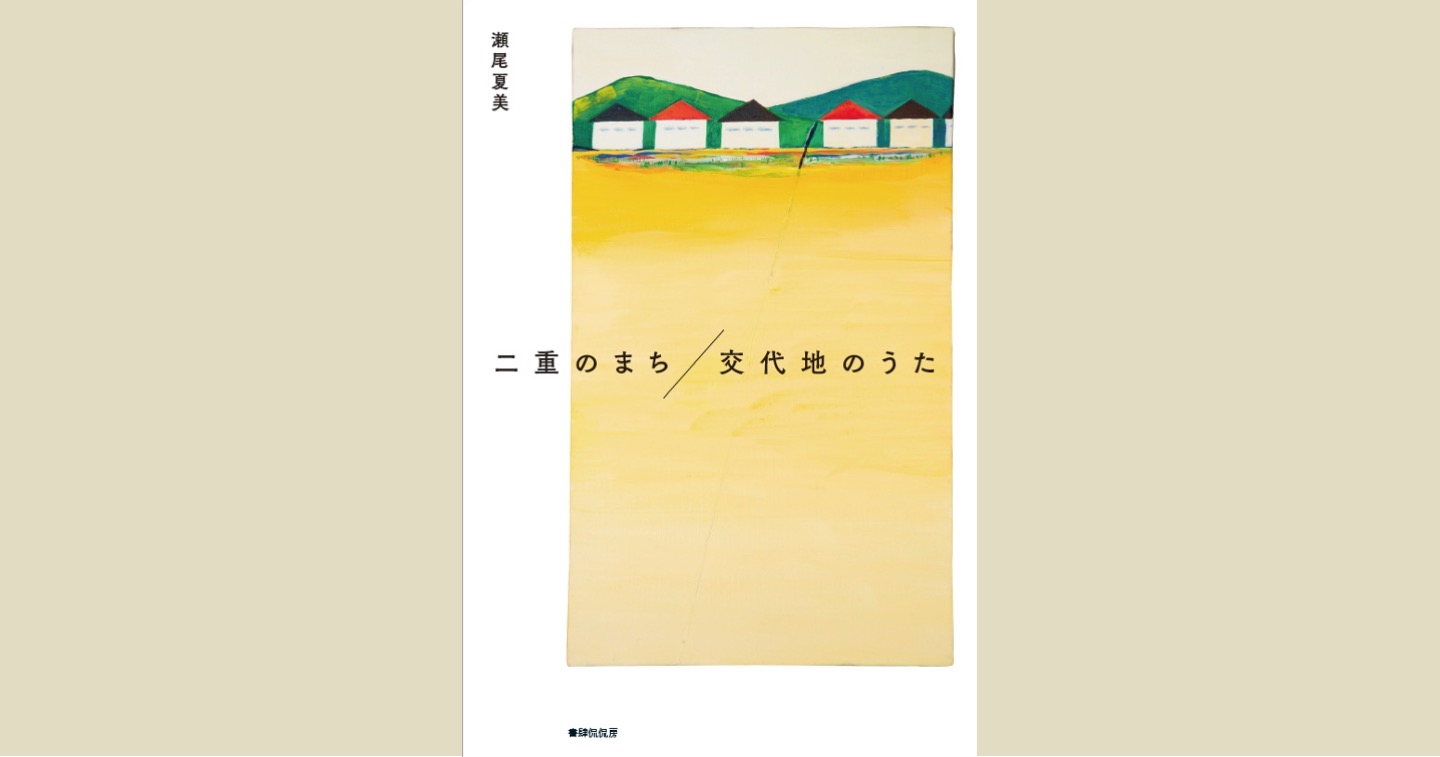大きな変化のなかで、小さな語りに耳を傾けること
先日、福岡では、1960年の創業以来愛されてきた老舗の「ロシヤ料理 ツンドラ」閉店を報せる記事が、大きな話題となった。後継者不在、新型コロナ、そして街の大型開発にともなう地価高騰を見越した経営判断が理由だった。社長による「福岡の変化についていけなくなった」という発言に、胸を痛めた市民は少なくない。
大きな変化のなかで、失われていく記憶がある。
これから紹介する映画と上記のエピソードは直接関係するものではないが、この記事はここから始めてみたいと思う。
それでは本旨へ。
まずは映画の共同監督をつとめた2人の作家とその活動について、紹介する。
画家・作家の瀬尾夏美と、映像作家の小森はるか。
2011年3月、東京藝術大学の大学院に進学が決まっていた2人は、東日本大震災直後の3/30にボランティアとして現地に入る。何か自分たちが出来ることはないかと模索するなか、避難所で足止めされていたあるおばあさんから、ひとつの頼み事を託される。「壊滅した実家とその集落を代わりに見て、撮っておいてくれないか」。カメラを通して記録し、定着させること。これが自分たちの果たせる役割かもしれないと2人は考えた。そこから様々な被災地を巡り、映像による記録作業を開始する。
そのさなかに訪れた陸前高田市で、別のおばあさんと出会う。話を聞いてみると、ものすごい勢いで言葉があふれ出た。このとき2人は、受け取ってしまった言葉を“次に渡す”こともまた自分たちの役割ではないか、と感じた。現地入りからわずか1ヶ月間で起きたこれらの体験を携え、4/25に東京で第1回目の報告会を実施する。
それから1年間、彼女たちはこの報告会の参加者とともに、毎月東北を訪れては東京へその状況を持ち帰るという往復活動を続けた。その間2人は、刻々と移り変わる現地の変化にもっと細かく気づけるようになること、そしてやはり“作品”としてこの経験を伝え、広めていくことへの必要性を強めていた。翌2012年の4月、2人は現地への移住を決めた。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
平日は現地のアルバイトで生計を立てながら、休日には被災地を訪れ「とにかく話を聞く」ことをはじめた。しかしそこから約2年間、彼女たちはついに作品として表現を発表することはなかった。語れなかったのである。それはまず、自分たちに話をしてくれる人、聞かせてもらう出来事のひとつひとつが、そのまま受け入れられるほど単純ではなかったこと。そして、語り継ごうとする自分たちはどうやっても当事者にはなれない、という事実があった。
語り継ぐべき物事の“語れなさ”と向き合うこと。
“語れなさ”を引き受けてなお、語り継ごうとすること。
これらが、以降の彼女たちの活動を貫くテーマとなった。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
その後2014年に『波のした、土のうえ』という映画作品を完成させ、ロンドンで発表。このときの観客の反応を通じて、彼女たちは自分たちの体験をただ“報告する”以上の手応えを得る。
それは、どんなに個別の出来事や人を扱ったとしても、それが物語や表現を備えた“作品”として届けられたときには、遠くの誰かの体験や記憶にまでちゃんと繋がることができる、という確信であった。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
かくして2人は作家になる。
この世界のなかで、“作品”を通じて人々の話を語り継ぐという役割を、ただしく畏(おそ)れながらなお、引き受けたのだった。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』について
ここまで詳細に彼女たちの来歴を紹介してきたのには、理由がある。
今回紹介する映画『二重のまち/交代地のうたを編む』が、上述してきた彼女たちの歩みを、ある4人の若者に追体験させる作品であるからだ。その体験を通じて、4人の若者と、映画の観客に〈語り継ぐこと〉について改めて思いを巡らせるドキュメンタリーとなっている。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
映画の舞台となる岩手県 陸前高田市は、震災の津波によって壊滅的な被害を受け、被災地最大級の区画整備が行われたまちである。
あの日の津波が、かつてあった建物や道路、そして人々の命や記憶までも、すべて呆気なくさらっていった。その後、この地には“復興”のための大量の土が盛られ、数年にわたる大規模な嵩上げ工事が施される。いま、かつてのまちは地面の下に埋め重ねられ、ぴったり整備された地平のうえには 新しいまちが生まれている。
この街に、ワークショップのために4人の若者がやってくる。4人とも陸前高田から遠く離れた場所から集まった“旅人”である。彼らは瀬尾と小森が考案した方式に沿って、それぞれ地元の人々の話に、耳を傾けることからはじめる。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
目の前で助けきれなかった誰かのこと。亡くした息子のこと。スマホの新機種入荷が遅れたこと。震災がもたらした他愛のない話から、想像を絶する体験談まで。4人はそれらの話を、これから先に語り継ぐべきものだと感じた。しかし、ここで彼らは葛藤をはじめる。果たして、当事者ではない自分たちに、それを語り継ぐ資格はあるのだろうか?と。
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
この圧倒的な“語れなさ”と直面し、真摯にためらう4人の若者の姿を、映画はまっすぐに記録する。そして4人を悩ませる難題は、しずかに映画の観客の方にも向けられる——私たちもまた、これほど慎ましく、畏れを抱きながら、誠実に相手の話に耳を傾け、向き合うことが出来ているだろうか?
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
誰かの話をちゃんと聞くことも、他人の話を伝え継ぐことも、本来これほどに“不可能なこと”だったのだと愕然とする。しかし、その営みを止めるわけにはいかないことは、映画を最後まで見ればきっとどなたにも理解されるはずだ。誰かにきちんと寄り添い、大切な話や記憶をていねいに聞き取り、語り継がれる場所には、か弱くとも私たちの心を照らす希望が宿る。
田島さんと〈記憶を語り継ぐこと〉について考える
今回記事にお招きするのは、福岡の出版社・書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)の田島安江さん。田島さんは、今回紹介する映画のなかで、4人の若者が朗読する物語「二重のまち」を収録した書籍『二重のまち/交代地のうた』を、瀬尾さんと一緒につくりあげた編集者である。
「二重のまち/交代地のうた」書影
田島さんと瀬尾さんの出会いは、同社が2020年4月に創刊した文字ムック「ことばと」がきっかけだ。「ことばと」は、芸術や文学など複数の分野で活動する佐々木敦さんが編集長をつとめ、ベテランと新人の作家を織り交ぜた編集方針で全国的に注目を集めている。昨秋発刊の第2号にむけて佐々木さんから提案された執筆者候補に、瀬尾さんの名前があった。彼女はここで初小説作品となる「押入れは洞窟」を発表する。
「瀬尾さんとは、すごい量の校正を重ねました。ちょうどご自身の撮影と重なってしまったせいで、明け方とか、変な時間のメールが続いたりもしました。瀬尾さんは言葉にこだわる人なので、本当に何度もやりとりを繰り返すんですが、その気持ちは私にもよくわかるので、印刷直前までずっと粘って、一緒にかたちにしていきました」
この協働作業で結ばれた関係と、出来上がった小説の手応えから、田島さんは瀬尾さんに、「押入れは洞窟」の単行本化を提案する。その打ち合わせのあとに送られてきた、彼女がこれまで活動を通して作ってきた小冊子や、震災以降Twitterで継続している大量の日記を丁寧に見返すうちに、まずはこの「二重のまち」を本にしたいと思った。かくして小説の出版より先に生まれたのが『二重のまち/交代地のうた』である。
「瀬尾さんが書いてきた詩や日記、散文などをまとめられたことで、この本はひとつの“記録文学”になったのではないかと思います。この一冊を、これまでの伝承文学はもちろん、純文学などとも並べて読んでもらえるものにできたのは、嬉しいことでした。そこにもう一つ、瀬尾さんが描く“20年後の世界”のドローイングの鮮やかな色合いが、不思議に明るい希望のようなものを思わせるんです」
映画『二重のまち/交代地のうたを編む』より場面写真 (C) KOMORI Haruka + SEO Natsumi
誰かの語りに耳を傾け、それを語り継ぐ。彼女たちが活動を通して重ねる営みは、福岡で出版を続ける田島さんにも通じるものではないかと尋ねてみると「ほとんど同じだと思う」という答えが返ってきた。
「昨年私は『少女たちがみつめた長崎 http://www.kankanbou.com/books/jinbun/society/0409』という本をつくりました。原爆が投下された当時少女だった、90歳過ぎの長崎県立高女の卒業生たちのもとへ、現役の女子高生たちが話を聞きにいくというものです。話してくれた元少女たちのなかには、いつか自分の経験を伝えなくては、と思っていながら、ずっとそう出来ずにいた方もおられました。戦争の話はされたくなかったんですね。そこに、当時の自分たちと同じ年代の女の子たちがやってきて、話を聞かせて欲しいと求められた。すると、ああ、せめて最後に伝えなきゃ、と語りはじめてくださったんです」
失われゆく記憶や物語を継承するには、まず “聞く”ことからしか始まらない。しかし語られた話を、実際には経験していない自分たちが語り継ぐことについては、瀬尾さんたち同様に迷いを抱く場面が生まれていたという。
「戦争も、震災も、時間が経つほどに、どんどん伝えるひとがいなくなります。当事者でない誰かが、語り部となることをためらったとしても、だからといってその話を伝えなくても良いことには、ならないと思うんです。長崎の元少女たちも『あなたが思うやり方で、私たちの想いを伝えてくれたら、それで良いんですよ』と仰っていました。伝えることそのものが大事だって。3.11もそう。誰かの想像力に繋げていくことが大事だから、やっぱり、書いて、話して、伝え続けないといけないんだと思うんですよね」
—
いまこの瞬間にも、耳を傾けなければただ失われていくだけの、誰かの記憶や物語がある。わたしたちがそれらすべてをすくいあげることは不可能だし、語り継ぐことだってまた容易ではない。それでも、大きな変化の渦中にある今だからこそ、こうした小さな何かに耳を澄ませ、心を寄せることにはきっと意味があるはずだと思うのだ。
映画は5月15日(土)より、KBCシネマ1・2で上映される。
「二重のまち/交代地のうたを編む」
(2019年/79分/日本)
5月15日(土)より、KBCシネマ1・2 ほかにて公開
HP:www.kotaichi.com
出演: 古田春花 米川幸リオン 坂井遥香 三浦碧至
監督: 小森はるか + 瀬尾夏美
撮影・編集: 小森はるか 福原悠介 録音・整音:福原悠介
作中テキスト: 瀬尾夏美
ワークショップ企画・制作: 瀬尾夏美 小森はるか
スチール: 森田具海
カラーグレーディング:長崎隼人
配給:東風
(参考・引用)
『二重のまち/交代地のうた』瀬尾夏美|エッセイ・評論|書籍|書肆侃侃房
『ことばと』vol.2|文学ムック ことばと|書籍|書肆侃侃房
【横浜市民ギャラリー】小森はるか+瀬尾夏美インタビュー
「素手のふるまい 芸術で社会をひらく」鷲田清一 (朝日文庫)