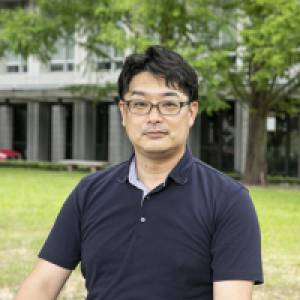テレビや新聞などのマスコミ,さまざまな公的機関の審議会の場で専門家の知見が求められるシーンは多くあります。専門家であるからこそ適切な答えを示すことができる。時にその発言が大きく社会を動かすことになる場合もあるでしょう。
一方で,この2年間,わたしたちの生活を大きく変えた新型コロナウィルス。歴史的に見ればこれまでも同様のパンデミックはあったものの,わたしたちが生を受けているこのタイミングでこのようなことに出会うとはほとんどの人が思っていなかったでしょう。この状況下で大きくクローズアップされたのは,誰にも未来がわからない状況の中での専門家の発言や予測でした。SNSなどを見ていると,その専門家の予測が「当たらなかった」としてひどく批判の対象になることもありました。「専門家の言うことは当てにならない」のではないかと。
今回ほど専門家であることの難しさ,力の無さを実感したことはありませんでした。大学の教員であること,専門家として何かを話したり,伝えたりすることの意味はどこにあるのか。片隅で細々と研究や教育活動をしている私のような人間でも,専門家であることの意味を深く考えさせられました。
そうした中で,手にしたのがこの本でした。自分自身が大学教員という専門家と世間的に考えられている仕事に就いていると同時に,大学生にはいかにして専門性を身につけるような学びを提供するか,あるいは子育て中の親として子に対してどのような学びの場を提供するべきかといったことを考える中でひとつのモノの見方を得たいと考えてのことです。
本書は,まず2人のプロスポーツ選手の物語から始まります。稀代の天才プロテニスプレーヤーで先日引退を発表したロジャー・フェデラーと,同時代に生まれ多くの伝説的な成績を残したプロゴルファーであるタイガー・ウッズです。今ではともにそれぞれの競技のトップアスリートとして活躍をしてきた2人ですが,その歩みは対照的なんだそうです。
タイガー・ウッズは2歳でテレビに出演して,すでにゴルフクラブを持ってコースに出て,10歳以下のクラスで優勝。その後もメキメキと実力を伸ばす息子を見て父親は「この子はゴルフのために生まれてきた。息子を導くのは自分の務めだ」とタイガーをプロゴルファーとして育てることを決めたそうです。8歳のときに初めて父親に勝ち,その後の活躍は誰もが知っているとおりです。
一方,フェデラーは歩き始める頃にはボールを蹴り始めたそうですが,子供の頃はスカッシュ,スキー,レスリング,水泳,スケートボードもして遊んでいたそうです。やがてバスケットボールやハンドボール,テニスも卓球も,とにかくあらゆるスポーツをしていたと言います。母親はテニスコーチでしたが,ロジャーの指導はしないと決め,彼自身がやりたいと思うスポーツに取り組めば良いと距離をおいていました。そうしているうちに13歳になるとロジャーは自らテニスを選んで本格的に競技を始めることになりました。しかし,両親は彼に対してほとんど何も言わず,ただ「ズルをするな」と伝えたと言います。また,あまりに強かったので上級生と同じコースで練習をしていても,彼自身は友達と他愛もない話をすることが楽しくて仕方なかったのだとも。楽しくスポーツに打ち込んでいた少年は気づけば世界のトッププレイヤーになっていたのですね。
このことは何を意味にしているのでしょうか。よく何か1つのことを身につけるのに,「1万時間の法則」があることを聞かれた方もいるでしょう。どんな分野でも専門特化した練習の時間数がスキルの伸びを決める唯一の要因になるのだと。タイガー・ウッズの事例はまさにこれを証明するようなものです。
しかし,また別の研究では次のようなことが言われています。近年のオリンピックで好成績を残せていなかったイギリスのオリンピックチームでしたが,2012年のロンドンオリンピックでは好成績を残しました。その選手たちが子供の頃から当該競技に対してどれだけの時間を費やしていたかを調べると,アスリートとして活動し始めた時期からの練習時間はそうでない選手と比して圧倒的に長いのですが,幼少期から青年期における練習時間は実は短いということがわかりました。その代わり,彼・彼女たちはさまざまな競技に取り組み,ゆっくり専門を決めていたのだと言います。これはサッカーの強豪国ドイツ代表の選手たちでも同じことが言えたそうで。早くから専門特化することが必ずしもその人の能力を伸ばすわけではないことが示されています。
つまり,ある一定のレベルに達するためには,幅広くさまざまなことを始めて,成長過程で経験を積み,多様な視点を持つことが必要だということを示唆しています。だからこそ,この本の表題が「RANGE」= 幅となっているのですね。そして,この本を読んでいると学校という場において教育に携わっている人間がいかに児童・生徒・学生と接することが求められるのか,私自身のあり方を改めて考えさせられることになりました。
本書では,その幅を持つ人となるために,わたしたちの学びの前提を見直すことを提案しています。学校には問題が明確でルールが決められている「親切な世界」が広がっていて,先生からフィードバックを得ながら努力によって上達可能な「親切な学習環境」が整えられています。しかし,社会に出ればさまざまな人がいて,ルールは必ずしも明確ではない場面によく遭遇します。類似したパターンも稀にありはするものの,基本的には繰り返し同じような事象が起きるわけではなく,問題も曖昧な「意地悪な世界」がそこには広がっています。筆者はそうした「意地悪な世界」においては「1万時間の法則」で狭い領域で専門性を高めていくことよりも,さまざまな課題があることを認識し,多様なことに取り組んでいきつつ,フィット感が高い領域を見つけた上で専門特化することを勧めています。
そうした学びの姿勢を身につけることで,社会の状況が大きく変化したとしても,他者から得られるアイデアや自分の中から湧き出てくるアイデアを結びつけて考えられるようになるのだと筆者は主張します。つまり,多様な経験が基礎となって創造的なアイデアが生まれてくるのだと言うのですね。まさにイノベーションです。それはあたかもチェスや将棋の棋士がこれまでの経験の中から(大量の棋譜データの中から)パターンを認識するように,初めて遭遇した場面であったとしても類推を働かせて解決策を見出し,実行に移して確かな成果を得ることにつながる。スポーツでも,仕事でも同じようなことは言えるように思います。
このように書くと,専門家の価値が減じてしまうように読めるかもしれません。が,そのように言って良いのでしょうか。大学教員という専門性の求められる職業に就いている私自身がこのようなことを書くのは少々違和感がありますが,恐らく「専門」というものの捉え方が鍵になりそうです。そして,ここまでのエピソードが「学ぶ」ということの本質を物語っていると言えるかもしれません。
大学で学ぶことの効用は,ある1つあるいは複数の視点(専門領域)を基軸にして,事象をその観点から見るといかに見えるかを訓練することにあるでしょう。それは「何かを形式的な知識として知っている」ということよりも,「知識を事象に適応できるかどうか」が重要になる場面です。大学1年生に対してこうした大学での学び方を話すとキョトンとした顔をします。また,大学生からの自己紹介で「知識をたくさん身につけたい」と言われることがありますが,それも「学ぶ」=「多くの知識を得る」ことだと思っているからなのでしょう。クイズ番組でさまざまな分野によどみなく解答する人たちはそれはそれですごいのですが,「知っていること」に価値を見出してしまう。
一方で,優れた研究者を見ていると,彼・彼女たちは一見突拍子もないような仮説(仮の答え)を提示しながらも,そこに真実があることを明らかにしようとしていきます。まさに,ピーター・ティールが新たな事業を興すのに「あなただけが知っている真実はなにか」を問うように。そう,専門的であるということは答えを出すこと,予言を出せるようになることではありません。適切な問いを立て,多様な答えがありうることを前提にモノゴトを組み立てていくことなのだと言えるかもしれません。
そして,このことは大学で大学生が今学ぶことだけを指しているのではなく,誰もが持つべき思考を行う上での大切な前提になることなのかもしれません。確かに多芸多才の人は面白くて,興味深いですものね。私も少しは何か特技と呼べるものを持ちたいものです。