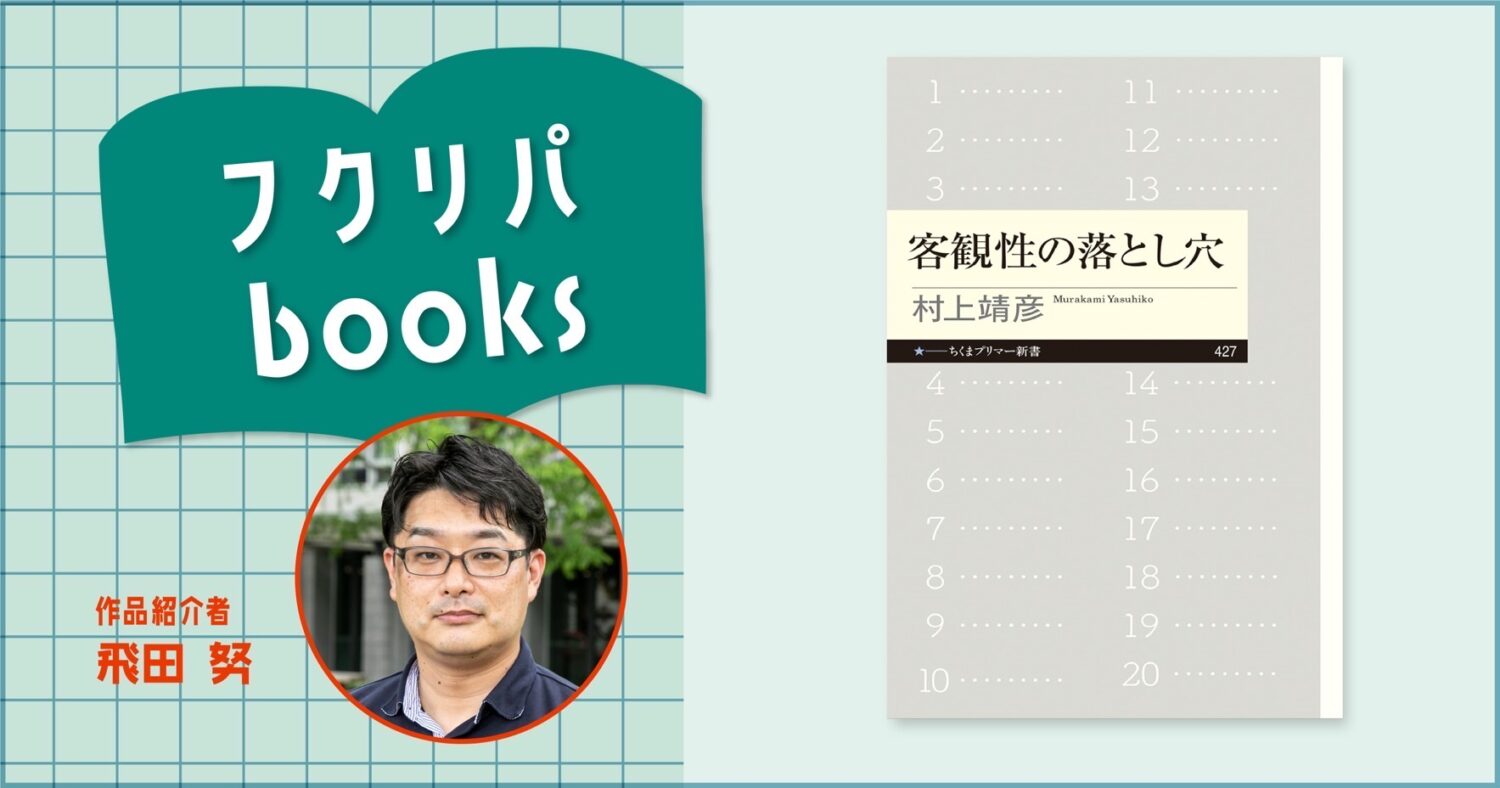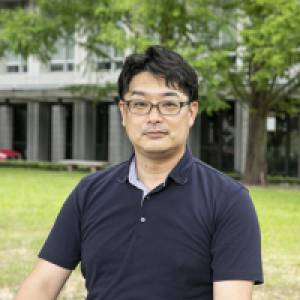「大切なものは目に見えない。」
このフレーズは,サン=テグジュペリの『星の王子さま』で知られるものです。これまでも,ここではモノゴトを見るときに「具体と抽象」という観点で把握することがいかに大事かを繰り返し述べてきました。結局,あるモノゴトにどのような意味を見出すかというのは,その人が持っている視点に依拠することだと常々感じています。
数値管理が悪でMVVが正義,という極端な傾向
先日,あるSNSに企業経営に関する本をもとに投稿をしました。そこには,これまでの企業経営は予算に代表される数値目標に基づいた管理が行われてきたとして,管理というムチで打たれることの引き換えに出世や安定的な給与,福利厚生によるインセンティブが与えられるとされていました。そして,これからの経営は,そのような管理ではなく,ビジョンとミッションの間でワクワクするストーリーと価値創造のアイデアが行き来するようなものでなければならないと指摘されています。
昨今の企業経営を論じるときに,MVV(ミッション,ビジョン,バリューの頭文字)の重要性が叫ばれています。このことを批判するつもりはありません。その通りだと思います。しかし,企業の存続のためには一定程度の利益が必要で,その利益を獲得するためには一定程度の管理も必要です。その管理の方法を取り上げて,どのような仕組みを作れば機能するのか,経営者は何を考えているのかを説明するのが私の専門領域である「管理会計」や「財務管理」と呼ばれる分野ですが,この視点から言えば,ビジョンとミッションだけで企業経営を語るのは違和感を感じます。もう少し言えば,企業が階層的組織になっていて,経営者,管理者,従業員という階層になっていれば,それぞれが見えている世界が異なります。

つまり,経営者の頭の中で組織成員を動機づけるためにMVVをどう書くか,どう浸透させるかという議論であれば筆者の説明は理解できるのですが,企業経営の重要な目的のひとつである利益を生み出し,事業を継続するという観点からは,立場の違いがある中でいかに組織目的や目標をどう共有するか,そこに会計数値を介在させるというのは当然のことのようにも思います。数値を使ったマネジメントに問題があるのではなく,そこにMVVに関連づけられた目標をどう設定するか,どのような意味を持たせるのかというところにこそ,マネジメントの肝があるように感じます。
「どこまで主観的に理解するか」
このように,見方を変えてしまえば,同じ企業経営のことを論じているにも関わらず,(最近の言い方で言えば)「解像度」が異なるわけです。言わば,「具体と抽象」ですね。そして,起きている現象を明らかにする研究をしている立場から言えば,「どこまで客観的か(理論に則っているか)」という議論を意識する一方で,そこで起きている事象を基礎に「どこまで主観的に理解するか」という観点も忘れてはならないと考えます。改めてそうしたことを考えることの重要性を気づかせてくれたのが,今回取り上げる『客観性の落とし穴』です。
この本の著者である村上靖彦氏は大阪大学大学院教授で,専門は「現象学的な質的研究」とされています。
私も専門外だから詳しくは述べることができませんが,先生は医療や貧困支援の現場に足を運び,当事者やサポートする支援者の語りに耳を傾けて分析するということを専門にされています。そこには,ひとりひとりの『主観』に裏付けられた語りがあり,その状況を語る本人たちはさまざまな表情で,言葉を選びながら話をしているのだと書かれています。こうしたインタビューや当事者ひとりひとりに着目して,そこから「真実」を得ようとしています。こうした研究アプローチのことを質的研究と言います。先生の研究アプローチはその語りの状況=現象に焦点を当てて,語る人から見える世界を大切にする考え方です。
一方で,この主観的なモノゴトの見方に対する疑念が近年Youtubeなどで提示して「論破だ!」というようなコンテンツが出てきたりもしています。(私のゼミや少人数教育の場ではそのようなことはありませんが,Twitterなどでは大学教員のぼやきとして)こうしたコンテンツを見て「論破だ!」とやったり,「客観性はどこにあるんですか?」という質問をしたり,人の話に耳を貸さないなんて例も出てきているようです。これもモノの見方だから否定することはしませんが,さまざまな答えがあり得るという立場で研究,教育に携わっている立場からすると,(もしこんなことがあれば)正直困ったものだなぁと思ってしまうかもしれません。
そもそも「客観」とはどこにあるのか?
経営学が含まれる社会科学領域で言えば,一定の尺度や量で測定する(例えば,会計情報もそうですし,アンケート調査の回答などもそうですね)ことによって,さまざまな状況を捨象して比較しやすくするという意味だとここでは考えておきましょう。行政でも政策を打つときには,患者が何人いるか,貧困層に該当する子どもはどれだけいるか,待機児童は,労働時間はと量で測ることがあります。また,これまでも学力を測る,活動の成果を測る場合には偏差値や生産性といった尺度を使って量的に把握するということをしてきました。
しかし,それはあくまでも情報の縮約の方法によって見え方が異なるだけで,その回答をした人の主観やどんな生活を送っているのかという情報はこぼれ落ちてしまっていることに気付かされます。
村上先生も本書の冒頭で「数値に過大な価値を見出していくと,社会はどうなっていくだろうか。客観性だけに価値をおいたときには,一人ひとりの経験が顧みられなくなるのではないか。そのような思いが湧いたことが本書執筆の動機である」(8ページ)と述べておられます。
情報を数値に縮約して扱うことは必ずしもすべてを説明することにはならない。という当たり前のことに気付かされます。要はどこからその事象を捉えるか,それによってどんな景色が見えるのかということにわたしたちはもっと心を砕かなければならないということなのかもしれません。
「主観」ではなく,「共同的な経験のダイナミズム」
一方で,だからと言って,すべての人の状況を把握して,折り合いをつけて意思決定を行うということも難しい。主観という「特別な」事例だけで判断することで全体最適を失ってしまうことも,これまでたくさんの事例で目にしてきたことでもあります。
そこで,村上先生は医療やケアの現場に足を運ばれた経験から,そこで起きている事象を見て客観に対置するべきは主観ではなく,「共同的な経験のダイナミズム」だと述べておられます。つまり,ひとつひとつの事象は当事者あるいは支援者,その状況を観察する人(観察者)の立場によって見え方が異なるだろう。しかし,互いの主観のやり取りを通じて見えるのは対話から生み出されるリズムだと言います。そして,そうした現象に法則性を見出し,「経験の内側に視点を取る思考方法」を提案されています。
こう書くと「経験の内側」とは個人の内面にある「主観」ではないかという意見もあるでしょう。それに対して,村上先生は次のような説明をされます。
「経験の内側に視点を取る思考方法」とは,自分自身だけでなく,他者の経験についてもその人の立場から記述するものであり,共感や感情移入を極力排除して,その人の個人の内面を個別的に記述しようというものであること。また,個人の経験は心のなかに閉じ込めることができず,対人関係や社会,歴史の絡み合いの広がりを描き出す試みだとも言います。つまり,「ひとりひとりの経験の個別性と重さを重視する」(136ページ)のだと述べています。
例えば,倫理観というものがどのように形成されてきたのかということを考えれば,それは誰か施政者が法律やルールという形で明文化して決めたことが定着したこともあれば,わたしたちの生活の中で暗黙的に形成されるものもあります。「個別の経験が生む『概念』が,誰にとって意味がある共通の『理念』として,倫理的な『普遍』を指し示す」(148ページ)ものでもあるのです。
冒頭で述べた企業経営のあるべき姿を文字で表したMVVも同じようなものかもしれません。同じ景色を見ていても人によって感じ方,捉え方が異なる。そうした中で,企業をある方向に導くために,自らの存在意義を問うために,創業者や経営者は企業内部において普遍的な価値観を根付かせようとしているのかもしれません。そこには,組織的な活動を導く視点を定義しながら,実はそうした人々の価値観が色濃く反映されるということをも意味します。まさに主観と客観の狭間にある価値観を組織マネジメントに反映させるかということかもしれません。
「客観的な視点から得られた数値的なデータや一般的な概念は,個別の人生の具体的な厚みと複雑な経験を理解するときに,はじめて意味を持つ。数値的なデータの背景には人生の厚みが隠れているのだ」(98ページ)
こうした指摘からは,わたしたちに今求められていることは,そこで起きている(直接的に見ているあるいは間接的に見聞きした)現象をどう捉えるかということに関して,さまざまな見方を学ぶ必要があるということかもしれません。私も質的研究を主として,経営者が経営管理システムをいかに構築しようとしているのかを観察しようとしていますが,医療やケアの現場,文化人類学的なアプローチから学ぶことが多々あります。その目の前の事象から真実をいかに紡ぎ出すのか。そこにある真実は何か。これはいつまでも終わらない大きな課題です。
ここでは紹介をしませんでしたが,本書の中では村上先生が直面されてきた医療やケアの現場の生々しいやり取りも記述されています。その記述を読んで初めて知ることも多々あります。改めて知らないことばかりだなと思い知らされました。ぜひ手に取ってお読み頂きたい1冊です。
■飛田先生の著書はこちら