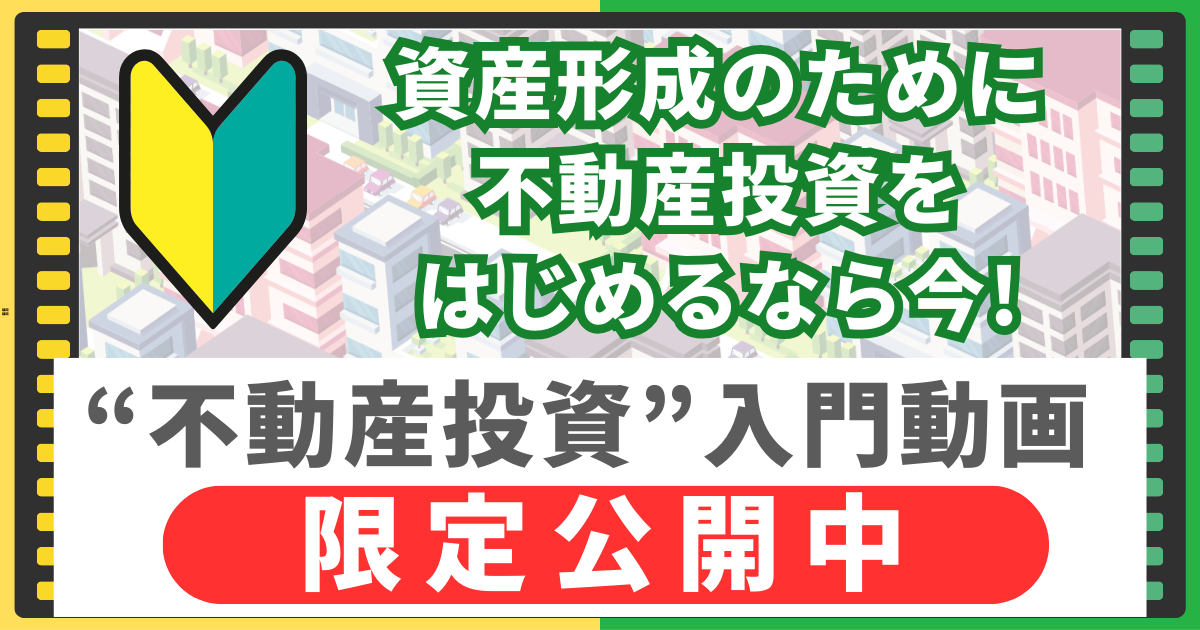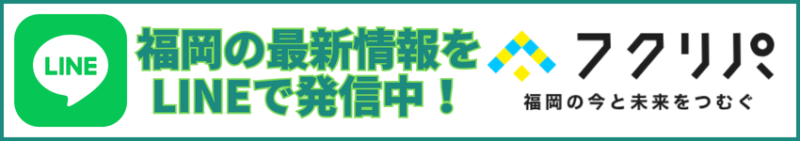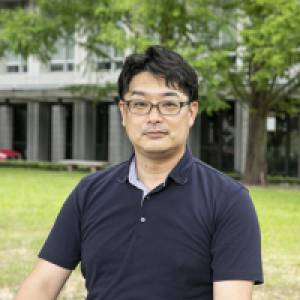この記事の目次
「まちとどう関わって生きていくか」なんて,学生時代は考えたこともなかった。
学生時代には街への思い入れもなかった1人の青年が,人に誘われて参加したゴミ拾いのボランティアを通じて,見方が大きく変化していく。掃除をしながら見た天神の朝の風景,人との何気ない会話,そこにあった“自分の居場所”の感触——それが今では福岡のまちづくりと人のつながりを支える「福岡テンジン大学(以下テンジン大学)」につながっています。
テンジン大学は肩書も目的も問われない,偶然の出会いが生まれる場所。ただし,それは単に「緩やかで自由な場」というわけではなく,便利になりすぎた都市のなかで失われつつある「余白」や「偶発性」をもう一度つくり直そうとする試みとも言えるかもしれません。

今回はその創設者であり,学長でもある岩永真一(いわなが・しんいち)さんにお話を伺いました。2010年初めに日本中で多くのコミュニティを基礎とした学びの場が作られましたが,テンジン大学もその中の1つでした。その創設者がどのようにしてコミュニティに興味を持ち,テンジン大学の立ち上げから現在に至ったのか。その歩みを紐解くことで「まちで生きるとはどういうことか」「都市と人との関係はどう再構築できるのか」をお尋ねしました。福岡生まれ,福岡育ちの岩永さんが語るテンジン大学の誕生の秘話から,変わりゆく福岡の街の姿,そして未来への展望までを深掘りします。
1人の青年がまちづくりに関わるまで
飛田 まず自己紹介とこれまでの活動について概要をお話し頂けますか?
岩永 岩永真一と言います。福岡市で生まれ育って一度も福岡市を出たことがありません(笑)。福岡大学を2004年に卒業したのですが,当時は就職氷河期末期でした。就職活動はかなり早めに始めていたのですが,最終面接でことごとく落ちるという現象に見舞われ,途中で就活を辞めてフリーターのまま卒業しました。
大学卒業の少し前に「グリーンバード」という街の清掃をするNPOと出会いまして,それに参加するようになりました。その後もグリーンバードに参加していたこともあって,徐々に天神のまちづくりに関わるようになりました。
そこで「こういう仕事をしてみたい」と思ったり,街の中で自分の居場所を見つけたという感覚も強かったので,ひとつの会社に入って居場所を見つけてキャリアを積むという人生設計ではない違う道を歩もうと決めました。働きながらもグリーンバードやまちづくりに関わるようなことを5年ほどやって,2009年4月に独立しました。そこから1年後にテンジン大学を立ち上げて今に至ります。
飛田 子どもの頃から街に対する帰属意識のようなものは強かったんですか?
岩永 むしろあんまりなかったですね。実は僕の人間関係はあまり広くなかったんです。地元の友達と親ぐらいなもので,街に対する憧れもなければ,何かインパクトが強く残っているということもほとんどないです。
飛田 そうした岩永さんが就職氷河期という自分ではどうにもできない外部環境があった中で,グリーンバードという活動に参加される。そもそもゴミを拾うとか、天神のまちづくりに参画しようと思ったのは、どういうきっかけがあったんですか?
岩永 そもそもまちづくりという言葉すら知らなくて。グリーンバードも本当にボランティアとかもあんまり興味なかったんですけど,天神自体も大学生の時はあまり好んで行かなかったんですね。人混みがあまり好きじゃなかったので。
ただ,ある時にたまたま誘われて行った掃除がすごく新鮮でした。僕の中で天神とかビジネス街の朝の風景を知らなかったので,「みんなこんな眠たそうな目で仕事に行ってるんだ」とか,「掃除しているとゴミがいろいろ落ちているけど,意外とみんなゴミをスルーしていくんだ」とか。たまに「ありがとうございます」と通行人に言われたりもするのでそういうのがすごく新鮮で面白いなと思いました。
もうひとつは,グリーンバードという団体自体がいろんな職業のいろんな年齢の人たちが参加していて,そういう人たちが集まる場に行ったのも初めてだったんです。いろいろ新鮮尽くしで,そこがだんだん居場所になっていったというのが大きいです。街中でもコミュニティっぽい感じで居場所って作れるんだというのがすごい衝撃でした。
掃除をすると街の風景が変わっていくのがわかるんですね。セミが鳴き始めるタイミング,桜が咲くタイミングとか,クリスマスのイルミネーションをつけるタイミング。そういうので街の風景が変わっていく面白さを感じ始めていた時に「まちづくり」という言葉を知りました。
2002年に博多駅がリニューアルされて,2011年に九州新幹線ができるという話が発表されたのをキッカケに,天神のまちづくりをみんなで盛り上げないといけないという空気になったんですね。その後に,僕は天神の街に関わり始めたんです。その時に市役所や西日本鉄道の人と出会って「この街をこうしたい」と言っているのがすごくかっこよく見えたのが非常に大きかったです。
飛田 街を通じて人を観察するみたいなところが、岩永さんにとっては非常にフィットしたし、そこで人と人とのつながりができたというのは22歳の岩永青年には非常に新鮮だったわけですね。
岩永 はい。グリーンバードは全国各地で活動を行っているのですが,それを立ち上げたのが長谷部健さんという,現在は東京の渋谷区長をやっている方なんです。当時,長谷部さんもたびたび福岡に来てくださったので,僕の中では「こんなすごい人と簡単に会えちゃうんだ」みたいな感じでした。働き始めてからも東京での仕事で困り事があって長谷部さんにご相談したんです。すると,1時間も経たずに解決してしまった。「人とのつながりってこういうことだ」というのが大きく,いろんな人とつながっておくと相談相手がいっぱいできるんだというのが大きいインパクトで,その後のキャリア形成にかなり影響を与えています。

長谷部さんが福岡に来たグリーンバード(2005年)
飛田 グリーンバードでまちづくりに関わりながら,お仕事はどうされていたんですか?
岩永 広告代理店で仕事したり,動画制作をフリーでされている方のアシスタントをしたりしていました。さまざまな方とお会いできる機会があって,とても楽しかったのを覚えています。しかし,ある日突然人事異動で違う会社への出向辞令が出たんです。当時の仕事が自分に合っていると思ったし,続けたい気持ちが強かったのもあって退職してしまいます。その会社ではインターネット広告の仕組みを学ぶことができたし,そこからいろいろ自分で動くようになりました。
そうしていると,グリーンバードを福岡で立ち上げた方が「アルバイトでいいなら来たら」と動画制作のアシスタント的なお仕事にお誘いいただきました。そこで1年半ぐらい働いて,主にイベント運営の仕事が多かったです。その後、ホームページなどを作る会社に転職をして,その後に独立をしました。独立した時の最初は,ホームページを作ったり,パンフレットを作ったりという広告の制作をフリーランスで始めました。
福岡テンジン大学開校前夜から大学の立ち上げに至るまで
飛田 そこからフリーランスとしてキャリアを積み始めるわけですが,テンジン大学の開校までにはまだまだいろいろあったのですか?
岩永 そうですね。東京でシブヤ大学が立ち上がるという話は,独立をした直後ぐらいに長谷部さんからも聞いていました。そのときに「いつか福岡でテンジン大学やります」みたいなことを,ノリで言っていました。そういう中でテンジン大学を立ち上げる可能性があるというのを模索し始めていたところ、2つのチャンスが来ました。
1つは,シブヤ大学が総務省の予算を得て,全国各地にシブヤ大学の姉妹校を作るという事業を始めていました。僕もその勉強会のようなものに出席させてもらっていました。もう1つは,福岡市役所の市民局からNPOやボランティア団体が人もお金も出し合って事業を作るという「共働事業提案制度」を始めるということで,グリーンバードにも説明に来られたんです。その時にテンジン大学を提案できると思って、その2つの機会をきっかけに一気に動き出したという感じです。
飛田 そこでテンジン大学を立ち上げることになったと思うんですけど、最初から順調に立ち上がっていったんですか?

開校式
岩永 「共働事業提案制度」に採択されたことで,それをもとに活動する基盤ができたというのは大きかったですね。自分でも独立して仕事を少し作ってきたので,生活できるぐらいの収入が得られるようにはなってきていました。さらに,「テンジン大学を立ち上げる」と宣言してから,周りの方も応援してくださるし,一緒にいろいろ手と足も頭も動かしてくれた方がたくさんいたので、それがすごく恵まれていました。
飛田 2010年の秋にテンジン大学が設立されたわけですが,あの時期はコミュニティ大学のような組織を街の中で作っていこうという動きが盛んになっていましたよね。その中で講義のコンテンツをどう揃えていくかというところの面白さと難しさがあったと思うんですが,どういったことを考えてコンテンツを作っていったんですか?
岩永 コンテンツを作り続けるというのはすごく難易度が高いんですね。でも,それまでの経験を通じて,フレームワーク化して,オペレーションをちゃんと組んで,それに乗っかれるようにしておけば,誰でも企画できるじゃないかという仮説が立てられていました。そこで,テンジン大学を立ち上げた最初の半年ぐらいでオペレーションを自分で作って,企画のフレームワークを作り,他の僕じゃない人に企画を立ててもらうという流れを何回かやってもらったら誰でも作れるようになったんですよ。
飛田 コンテンツを標準化したわけですね。
岩永 はい。これは自分がやらなくてもできると思って。立ち上げた時のコアメンバーはいましたけど、ファンメンバーも一緒にやりながら、僕以外の人たちが自由にコンテンツを作るということが可能になりました。

都市高速での授業(2013年)
飛田 岩永さんが無理やり主導してやるというよりも,そこに関わる人たちで「こんなの知って欲しい」とか,「こんなことを知りたい」と思っている人たちがもう勝手連的にいろんなアイデアを出してくれるフォーマットができたというのが、今のテンジン大学にとって大きかったってことですね。
岩永 はい,そうです。もうコミュニティみたいな感じなのができ始めて,さらにその中で「こういう面白い人がいる」とか「こういうことをやってみたい」という人の背中をひたすら押すというファシリテーションをやることで,勝手に企画が立ち上がって、勝手に形になって,勝手に人が集まって、動いていくみたいなのが次々に起きたので。
飛田 関わる人たちのリーダーシップを引き出したわけですね。
岩永 はい、SNSがまだそんなに来てない時でしたし,コミュニティがあんまりなかったのもあって,テンジン大学が福岡になかった最初のポジションを取れたというのも非常に大きかったですね。今でも本当に多様な方が来てくれます。
僕は学長として代表なんですけど,関わるみなさんと同じ目線で,同じポジションで一緒になって語るというスタンスを取るようにしているんですね。おかげさまで,みなさん本当に自由に発言しますし,主体性みたいなのが勝手に育つというのがわかりました。この点は今の人事系の仕事とか、ファシリテーションの仕事にかなり生かされています。
飛田 テンジン大学の特徴ってあるんですか?
岩永 それは街との距離が近かったり,街との接続をちゃんと意図的にやっているというのは他とはちょっと違うかもしれませんね。いわゆるコミュニティ大学って文化とかスキルを学んだり,趣味のことをやるみたいなのが結構多いんですけど,テンジン大学は街歩きとかもよくやってますし,天神とか福岡のことを知るみたいな授業も割と多いんです。そういうのは他にはあまりないって聞きますし,逆にちょっと意外でした。僕はWe Love天神協議会にも関わっていたので,街の中でいろんな人たちと出会うという仕掛けを結構やっていたので,それが特徴かなと思っていました。
飛田 そこに福岡らしさみたいなものを感じることはありますか?
岩永 テンジン大学を経験して,仕事の都合で他の地域に引っ越されて,その場所のコミュニティに参加した方が言うには,「テンジン大学はその福岡の街を知ろうみたいなテーマで人が集まるんですよね。福岡,すごいですよ」みたいなことを言ってくれたんです。

まちあるき授業(2014年)
飛田 福岡の人って本当に福岡が好きですよね。
岩永 そうなんです。で,そこで「福岡の人って福岡好きですよね」と言われたので、初めて認識したというか、「こんなにたくさん人が来てくれるんだ」みたいな。知らなかった一面を感じました。
飛田 テンジン大学に関わっているとか、授業を受けに来る受講生の皆さんって、福岡の人と、出身が福岡市外の方って割合決まってたりするんですか?

授業風景(2016年)
岩永 そこも一時期アンケートなどでデータを取っているんですけど,割と動いている,転勤で来ましたという人も多いし,出ていくという人も割と多いというのが,長く続けていると分かってきます。
僕の中で大きかったのは,2011年,12年ぐらいに福岡市の総合計画の審議会委員をやったんです。その時に福岡市民の統計データをたくさん見てかなり解像度が上がりました。福岡はたくさん人が入れ替わっているんだとか。そこで見た統計データとテンジン大学で取っていたデータが似ていて,「だからこうなのね」みたいなのがすごく多かったんです。
飛田 そのあたりの話って以前フクリパにも記事で書かれていましたよね。
岩永 はい,その通りです。
>>福岡人が「福岡っていいところやろ?」と言ってしまう深い理由!?
https://fukuoka-leapup.jp/city/202004.36
テンジン大学というコミュニティの変化
飛田 創立から15年,16年目ですかね。もう長いこと活動されているので,変わる部分と変わってない部分というのは感じることもあるかと。どういったところが設立当時と変わっていて,どういったところが変わってないなって感じられますか?

高校生が企画した授業(2015年)
岩永 テンジン大学は僕が学長というところで,それが唯一の色っぽくなっているんですね。立ち上げた当初は28歳だったので,若者の立ち上げたコミュニティという印象をみなさん持ってくださっていました。だから思いもありましたし,本当に若い人たちが集まりやすかったです。大学生が集まりやすかったです。2011年の東日本大震災のような社会的背景もあって,テンジン大学が注目を浴びやすかったのもあり,比較的多くの人たちに行き渡りました。設立当時20代,30代が多かったんですけど,今15年ぐらいたってそれがスライドしてきている感じがします。なので,ボリュームゾームは30代後半から40代ぐらいになっています。
飛田 なるほど。他に特徴みたいなものは感じられますか?
岩永 コロナ前後の違いなんですけど,50代,60代の方々がかなりアクティブになりましたね。それまでテンジン大学にあまり来てなかった方が,急に来られるようになったんですね。そこにユーザーの質の変化のようなものを感じます。
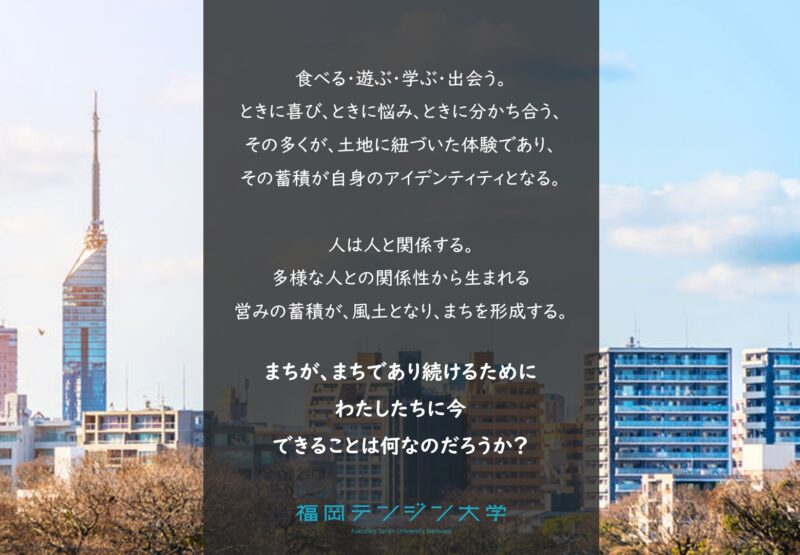
テンジン大の方針検討画像(2025年)
飛田 50代,60代が行くようになったというのは時間ができたからなのか,アイデンティティ・クライシスみたいなのを感じることがあったのでしょうか?
岩永 影響している気がします。恐らく飲み会とか減ったでしょうから,人との出会いにその世代の人たちの方が飢えているんじゃないかなと思います。
飛田 いわゆる飲み会で作られたコミュニティの代替に変わっていったというのがあるってことですね。
岩永 逆に昔に比べて20代があんまり来てないのもあります。
飛田 そうなってくると,テンジン大学の課題というのはいろんな人が混ぜこぜになるのはありがたいけれども,平均年齢が上がっていくというのも課題ですか?
岩永 昔からいる人は課題っぽく捉えちゃうんですが,この10年ほどで福岡の色が変わっていったのを感じていて,テンジン大学を立ち上げた時は「福岡の街を世界で一番魅力的な街にする」って言って開校したんです。けど,世界の中でも福岡が少し知られるようになったりとか,活気のある街というポジションはちゃんと取れたかなと。そういう意味でのテンジン大学の役目は終わったなと思っています。
むしろ,世の中から偶然のコミュニケーション,偶然の出会いとか,目的ではない出会いがすごく減っているので,そういうのをちゃんとデザインしてあげたりとか,ファシリテートすることで,予期せぬ出会いとか,予期せぬコミュニケーションみたいなのをちゃんと作れるような人を育成する,勝手に育成されるようにするのがテンジン大学の次の役目じゃないかというのを最近話し合っています。
テンジン大学から見る福岡の未来への展望
飛田 その考え方だとあんまり年齢とか関係なさそうですね。と同時に,天神はこの数年で大きな変化を遂げています。天神ビッグバンを岩永さんは今どうご覧になっているんですか?
岩永 今感じるのは,余白の部分がちょっと消えていっていることですね。街の中にあったちょっとした余白,「ここでこんなことを勝手にやっていいんだ!」みたいなものがほとんどなくなってしまった。以前は「この時間は何も使ってないから,いろいろ勝手にやっていいよ」って言ってくださる方が本当にたくさんいました。しかし,今はテンジン大学が活動できるスポットが本当に減った感じがします。
飛田 ワンビルができて,天神コアが中心部にあったときと印象が全く変わってしまいましたよね。余白がない,スペースが物理的にも減っていっているという中で,ここをもうちょっとこうできたらいいなというのは、なんかアイデアがあったりするんですか?
岩永 街を消費者として暮らす人が今どんどん増えているので,天神にあった余白部分が生まれないのかな。この街を面白くするために,一見すると無駄みたいな感じがするけれども,不思議だけど面白いことをやってくれる人が増えないといけないと思っているんですね。そういう人を応援する空気と,そういう人たちをパトロン的に見てくれる人が増えないといけないと思っているんですけど…。応援してくれる人ってどんな人だろうと思うと、最近あんまりイメージできなくなってきています。
飛田 わかります。天神にある公園でも,公共スペースにしてもイベントがたくさん行われるようになっている。でも,それが規格化されて,自由度が失われているのはすごく感じます。ルールに則って,安全に,誰もが楽しめる場にするために取り組まれているんだろうけれども,画一的でコンテンツの中身だけが少しずつ変わっている。それにコロナが来たというのもあるのでインパクトありそうですよね。では,これに関連して,福岡または天神の未来というのを、岩永さんはどういうふうに見ていますか?
岩永 今,天神という街の人格というか,「街格」みたいなのがあるとしたら,まさにアイデンティティみたいなのが切り替わろうとしているタイミングだと思います。そのときに天神がどういう方向に動いているのか,それを誰もコントロール,元々コントロールしてる人なんていないんですけど,リーダーっぽい人もいないですし,「こういう方向になれば」って言う民間人もいないですし。地元の人だったり,民間事業者が「この街をこうする」みたいなのを掲げつつ,アイデンティティをみんなで作るみたいな動きがないと,精神的焼け野原になっていきそうな気がしてます。
飛田 わかります。福岡の心のよりどころ的なポジションをテンジン大学は担っていくというのが1つの目標ですね。
岩永 担っていくというと、そんなに自信ないんですけど、プラットフォームを創るという形でキッカケにはしたいなと思います。
飛田 最後に,岩永さんからお伝えしたいこととかありますか?
岩永 今年,久しぶりに西鉄さんの本社が天神に戻ったので,この7年ぐらい天神で働いたことがない社員さんが増えているそうなんですね。そこで,先般,その方たち向けに天神のことだったり,西鉄が天神の街でやってきたことを話して欲しい,街歩きして欲しいというオーダーを頂きました。これがかなりインパクトがあったようで「こういうことが大事だな」みたいなのがすごい伝わったんですよね。飲料メーカーさんの九州支社で働く人たちも九州出身じゃない人が7割ぐらいいて,そういう方々は九州の人,九州の土地の特徴みたいなこととかを話せないので,九州の文脈みたいなのをちょっとぐらい知れるようにセミナーして欲しいというオーダーをもらいました。

西鉄社員向けまちあるき(2025年)
飛田 まさにアイデンティティ・クライシスですね。
岩永 まさにその通りです。本当にアイデンティティ,自分がなんでこの土地で生きているのか,働いているのかみたいなことを語れなくなってきているんだなというのはすごく感じます。だから,アイデンティティ教育というか,文脈教育みたいなのが,街にとってめちゃくちゃ今後大事だなと思います。
飛田 今,都市部でも地方と呼ばれる場所でも,消費者が消費しているものってほとんどがナショナルブランドですよね。だから,日本のどこにでもあるものなんですよね。そう考えれば無理やり東京に行く理由ってないんだけども,「東京に行くのが良いんでしょう」みたいな。街に対する愛着もそうだし,消費するということが画一的になってしまっている。こうしたことが街づくりにも現れちゃってるというイメージですよね。
岩永 はい。
飛田 となると,これからのテンジン大学が果たす役割をどう捉えていくか。とても楽しみにしています。今日はお忙しい中,ありがとうございました。
岩永 ありがとうございました。
ふりかえり
みなさん,いかがでしたか?
テンジン大学が大切にしてきたのは「偶然の出会い」と「人との関係を耕す時間」。目的や肩書にとらわれずに,誰かと交わり,街の空気に触れながら,自分自身のあり方を問い直せるような『場』をつくること。岩永さんはそれを天神という街のなかで丁寧に育ててきました。
しかし,街の再開発が進む中でかつてあった「余白」は少しずつ姿を消し,偶然のコミュニケーションが生まれにくくなっているのも事実です。都市の機能性が増す一方で,人と人との関係が分断されてしまう。そのギャップに岩永さんは強い危機感を抱いています。
テンジン大学はそんな変化のなかでも,人と街とを結びなおす場であり続けようとしています。学びを通してつながること。街を自分の言葉で語れるようになること。そして,誰かの「やってみたい」を応援できる関係が生まれること。テンジン大学の存在は,福岡のこれからにとって静かだけれど確かな希望なのだと思います。