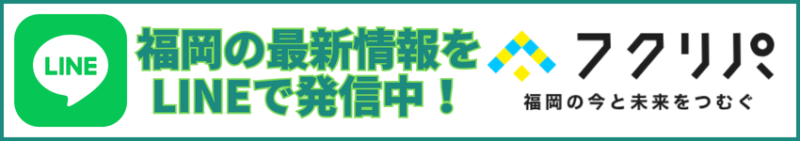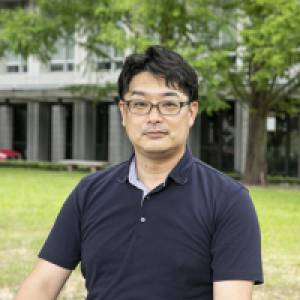地方創生,地域活性化という言葉が世に出てから長い時間が過ぎました。しかし,急激に進む人口減少の中,それぞれの地域が持つ課題が多様であることもわかってきました。
「自分が生まれ育った場所をより良くしたい」
「地元に貢献をしたい。しかし,どこから始めればいいか分からない。」
そんな思いを抱える若者は少なくありません。福岡で過ごした学生時代に地域課題と出会い,福岡でスタートアップや教育事業の実践を積み重ねた平野賢正さんは,2024年に地元・下関に戻りました。学生時代から「地域」と関わってきた彼がなぜ地元に戻ったのか。そして,今何を見つめ,誰とどのように地域と関わっているのか。福岡・東京・下関という3つの都市を通して地域と向き合い続けてきた歩みを振り返ってもらいました。
下関から福岡へ 大学進学と学生生活で得たもの
飛田 今日のテーマは福岡で得た経験を地元に還元するというものです。福岡は九州各地から進学や就職を機に若い人たちが引っ越してくる一方で,大学の進学実績等を見ると半数以上が関東・関西の企業に就職し,福岡を出ていくという現実があります。そうした中で平野さんは山口県下関市出身で大学進学を機に福岡で暮らすようになり,最初のキャリアも福岡で積まれることになりました。そして,東京での就職を経て,回り回って今は地元の下関で暮らしておられます。そうした平野さんにとって,福岡で得た経験,福岡から見える景色,そして今下関に暮らしながら働くという時間をどのように過ごしておられるのかをお伺いできればと。まず,自己紹介を兼ねてこれまでのキャリアと今のお仕事について教えて下さい。
平野 よろしくお願いします。平野賢正(ひらの・けんせい)と言います。山口県下関生まれの31歳です。高校まで下関で暮らし,大学から福岡に出ました。九州大学工学部在学中にインターンシップを始め,学生と一緒に地域課題の解決や新規事業の開発などを行う活動をしていました。そのままインターン先でもあったナレッジネットワーク株式会社に入社し,数年間働いてきましたが,30歳を機に自分のキャリアを改めて見つめ直し,東京のHR Techベンチャーに転職しました。1年弱東京で経験を積んだあと,改めて自身のフィールドを地域に移すべく,昨年12月に下関に戻ってきました。現在は下関を中心に中小企業のDX支援,採用支援や行政関係のお仕事などを仕事にしています。また,Regional Innovators Labという任意団体を立ち上げ,下関で社会人が学んだり,交流する場所として「関門大学」という取り組みを始めたところです。
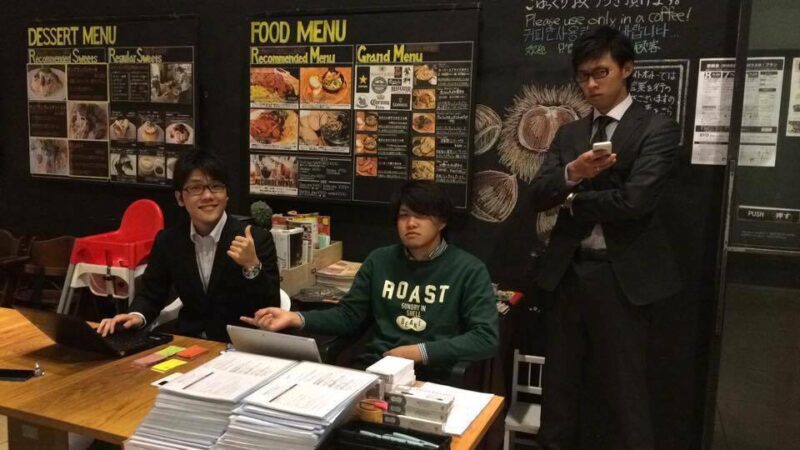
飛田 さっそく大活躍ですね。さすがのバイタリティ。では,まず下関で生まれた平野少年が大学までの間,どのように過ごしてきたのかをお話しいただけますか?
平野 幼少期は内向的だったと思います。ただ,小学校に入ってスポーツ少年団に入ってからは,中高でサッカー部のキャプテンをやったり,体育祭の応援団長をやったり,人前に立つことが自然と増えていきました。自分で何かを主張していくというよりは,「そろそろ誰かやらないとね」っていうときに,空気を察してやるという感じだったと思います。
大学進学を考えた時に,自分は航空宇宙系に興味があったので下関を出るという選択肢しかなく,東北大学,名古屋大学,九州大学のいずれかの大学を目指そうという感じでした。ただ,受験期に東日本大震災があったり,試験問題の傾向などから考えると九州大学を目指すという選択肢に絞られていきました。福岡に特別な憧れがあったわけではなくて,あくまで現実的な選択でした。
飛田 実際,福岡での生活はどうでしたか?
平野 これもあるあるだと思うのですが,大学進学と共に福岡で暮らし始めてから最初は,正直受験で燃え尽きていました。受験が終わって,目的もなく,普通の大学生をしていたというか。サークルとバイトをして,特に将来のことを考えるでもなく過ごしていました。2〜3年はそんな感じでしたね。ただ,3年生になって就職活動が視野に入ってきたとき,「このままでいいんだっけ?」ってふと思ったんです。
当時は福岡市も「スタートアップ都市宣言」をしたばかりで「スタートアップ来るぞ」という空気感がありました。そんなときに九大に孫泰蔵さんが来られたんですね。私自身は特にスタートアップに興味があったわけではなく,むしろ当時流行ってきた「パズドラ」を作ったガンホーの創業者の1人だというくらいの認識で,面白そうだからと友達を誘って話を聞きに行きました。そうしたら,その話が面白くて,ビジネスをする,何かにチャレンジしてみようという気持ちになりました。
その頃はインターンという言葉もようやく出てきた頃で,今ほどインターンが当たり前ということはありませんでした。ただ,就活中のある機会に,後のインターン先の経営者から「九大生は頭でっかちなんだよね」と言われ,その会社でインターンをすることにしました。しかも,これまた当時は一般的ではなかった休学を4年前期が終わるタイミングで決断しました。周りは就職活動を始めていた中で,僕は違う道を選んでみようと。
飛田 そのインターンでどんなことをやったんですか?
平野 その会社は,先程もご紹介したように,当時注目され始めていた地域の課題解決や新たな技術を活用した事業開発などに取り組んでいたので,僕もそのような活動を行うようになりました。具体的には,佐賀県伊万里市で地元のご当地検定をアプリ化する企画をしたり,コワーキング・シェアオフィスの立ち上げなどに携わりました。留学生向けの地域ツアーを設計するようなこともありました。チームで何かを形にして,それが地域に届く。そのプロセスにすごく手応えを感じました。それまで,地方創生とか地域活性化って,どこか他人事だったんです。でも,現場に行って,いろいろな方と話して,動いてみると,たくさんの気づきを得ることができました。

飛田 現場で実際に地域の人たちと関わることで,それまでとは違う感覚が生まれたんですね。
平野 はい。それまでは「地域活性化って,行政とか専門家がやるものでしょう?」って思っていたんです。でも実際に地域に行ってみたら,住んでいる人たちは「このまちをなんとかしたい」と本気で思っている。けど,何をどうしていいかわからない。その間に立って,少しでも動く役割を果たすっていうのは,自分にもできるかもしれないと思いました。僕は会社側で学生を組織化してマネジメントをしながら,現地の人たちと連携しながら活動していました。伊万里市は大学が無かったので,当時は「福岡から学生が来て何ができるの?」と思われていたかもしれないんですが,プロジェクトを重ねるにつれて,伊万里市に行く機会も多くなり,現地の方々と関わる機会も増えてきました。その中で,ある日,いつもなら「今日はどうしたの?」と聞かれていたところが「こんにちは」と,そこにいるのが当たり前かのように接してくださるようになってから,下関・福岡に加えて伊万里市が第三の故郷のように思えてきました。自分の存在が歓迎されているという感覚を持てたのは大きかったです。
また,佐賀県以外の地域に足を運ぶにつれて,そこに住まざるを得ない人,誇りを持って住んでいる人がいて,地域の見方が変わっていくことに手応えを感じていました。
飛田 そのあたりから「地域で仕事をする道があるかもしれない」と思い始めた?
平野 そうですね。結局,休学期間は気づけば2年半になっていました。理系だと大学院(修士課程)を修了して就職する人も多いので,ある意味大学院を終えたのと同じ年限で区切りをつけようと。そのインターン期間でさまざまな学びもあったし,新規事業開発できたり,福岡にさまざまな起業家,東京などで活躍している方々が来てくださって,幸い私もお会いできるようなポジションにいました。そうしたこともあり,「地方でも面白いことができるかもしれない」と思うようになりました。そこで,自分も福岡で仕事をしてみようと思うようになりました。
福岡で働く スタートアップブームの中でキャリアを形作る
飛田 確かに2010年代なかばの福岡って,スタートアップ支援で今以上に熱があった感じがしたよね。FGN(Fukuoka Growth Next)ができたり,いろんなイベントが立ち上がったり。とにかく多くのアントレプレナー(起業家)が福岡に来てくれていた。
平野 はい。就職で東京のベンチャーも考えていたんです。だけれども,最終的には福岡で働くことを選びました。確かに東京で働く,ベンチャーで働くというのも魅力的でした。でも,そこで働き始めるとあくまでもいち社員に過ぎなくて,経営者や起業家と会ってお話する機会は得られないかもしれない。もったいないなと思ったんです。むしろ,「福岡にいることで会える人たちがいる」「福岡にいることでできることがある」と思えた。地方に残るというより『福岡で続ける』という選択に確かな意味があると感じました。
福岡って東京の経営者たちがわざわざ来てくださる場所なんですよね。ラッキーなことにそういう場所にいたから「あの若手面白いんだよ」と言ってもらえることもありました。
飛田 それは20代でなかなか得られない経験ですよね。

平野 はい。加えて,就職した会社では福岡市が主催していた学生向けのスタートアップ支援プログラム「ビズチャレ」の伴走をさせてもらったり,新規事業としてドローンスクールの立ち上げや運営,子ども向けのプログラミング教室なども手掛けていました。
しかし,そうしたタイミングで新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが起き,それまでと同じような活動ができなくなってしまいました。
そうした中で,会社としても次の一手を考えなきゃいけない。そこで学生時代の活動の中でも培ってきた「テクノロジーの活用」で新規事業を立ち上げました。世の中的に完全にオンラインへの移行の流れがあったので,セミナーのオンライン配信やオフライン+オンラインのイベント配信,オンラインに適した企業イベントのコンサルなどの仕事も請け負うようになりました。新しい領域で時代に適した事業の立ち上げができていた一方で,自分自身の力でどれだけ会社や売上に貢献できていたかというと,満足が行かない部分もありました。
もう一度,自分を試す 東京での挑戦と再考の時
飛田 となると,パンデミックは社業も苦しくなる中で,自分のあり様を見直す時期にもなったってことですね。
平野 はい。そうですね。2023年から2024年になるとコロナが落ち着きはじめて,福岡を中心に手掛けていたプロジェクトも一区切りついたように感じていました。先ほどお話ししたように,自分自身の会社への貢献度なども考えると,『数字』に貪欲かつ自分の力が試される環境に飛び込んでみたいという気持ちも芽生えてきました。なにより,当時は学生と一緒に新規事業などに関わったり,学生へアドバイスしたりする機会があったのですが,福岡で働くことに意義を伝えながらも「あなたは東京で働いたことないでしょ」という声があるのかもしれないと勝手に思い込んでいたのかもしれません。
飛田 なるほど。そして,東京に行かれるわけですが,どんな会社に就職したのですか?
平野 転職支援サイトを活用して就職活動をしたのですが,その時の条件は「数年で上場する可能性がある」ベンチャーでした。上場前から働き始め,その会社が上場するまでのプロセスを経験できればという考えでした。そして,就職したのは採用支援サービスを展開している事業会社で,それまでの仕事の中で採用領域に関心があったこと,その企業がブランディングを重視した採用支援をしていたこともあって将来地域に戻ることを考えたときにブランディングを学んでおこうという考えもありました。
飛田 でも,実際働き始めてみると難しいこともあった。
平野 東京に出たのは,「自分の実力を測ってみたい」という思いが強かったんです。「福岡では会社や周囲のサポートがあったけど,それがなかったら自分はどれくらいできるんだろう?」というのを試したかったんです。ただ,いざ転職した後に,企業のカルチャーが自分にはあまり合っていないと感じるようになりました。さらに,想像していた以上に経営層との距離もあったので,自分がイメージしていたベンチャー企業とは少し違ったかなと思い始めました。
そうして退職してフリーになっているときに,東京での転職を考えていましたが,これまでの繋がりの中で,自分が役に立てる企業はないか?ということで,SNSで「今フリーなので,何かお手伝いできることがあれば声をかけてください」と投稿したんです。そうしたら,結構いろんな方が声をかけてくださって。その中で,僕が尊敬している北海道の厚真町に拠点を構える企業から「ちょっと来てみない?」と連絡を頂きました。現地で活動していた会社は,地域の課題解決を「みんなの力」で取り組もうとしているところでした。厚真町は人口4,000人程度の小さな町ですが,危機感の共有度合いがものすごく高いと感じました。だから,誰かが困っていたら,それを“自分ごと”として拾い上げて動く文化が醸成され始めていると実感しました。
でも,現地で動きながらずっと考えていたのは「このエネルギーを自分はどこに注ぎ込むべきなんだろう?」ということでした。
厚真で起きていることには共感できる。面白さも感じる。でも,同じように地域のために役に立つのであれば,地元である下関市でも同じなのでは?と感じるようになりました。ルーツもあり,家族もいる場所のほうが,より深く長く関われるんじゃないかと。
そこで下関に戻るという選択肢が出てきました。もちろん仕事をどうするか,生活をどうやって成り立たせるかという問題はあったのですが。
地元に戻るという選択 下関で関わりを作る日々
飛田 東京に行ってキラキラのキャリアを築けたわけではないけれども,学生時代から社会人にかけて積んだ経験がここで生きてきたわけですね。自分が寄って立つべき場所が地元である下関だった。
平野 はい。下関に戻ってきたのは2024年の12月でした。高校卒業以来久しぶりに地元に戻ってきたわけですけど,やっぱり福岡や東京で見てきたものとは,いろいろと感覚が違うなと感じています。僕はもともと,教育とか人材育成,地域の未来づくりといった文脈で仕事をしてきました。福岡でも東京でもそういう仕事をしてきたし,そこで使われていた言葉やフレームワークも自然に身についていたんです。
でも,思っていたよりも,地元の状況を「わかっていなかった」というのを日々実感しています。下関に帰ってきて思うのは,東京や福岡で行われている議論やフレームがそもそも通じないこともあるということです。福岡や東京で「これが大事」とされていた価値観をそのまま持ち込もうとしても,前提そのものがズレてしまう。
というのも,下関のような中核市(※下関市は人口25万人ほどで山口県では最大の都市)って制度や枠組みはある程度あるんですが,その運用が十分に機能していないことや担い手が見えにくかったりすることがあります。地方の小規模自治体や都市圏のように「極端な不足」や「極端な競争」があるわけではない。その分見えにくい課題が堆積しているように感じます。だから,よくある「こうすればうまくいく」みたいな型や施策を持ち込むだけではない一工夫が必要。なので,今はいきなり自分の考えやフレームを持ち込まずに,まずは“現場で何が起きているか”を丁寧に観察して会話することから始めています。
飛田 となると,ある程度自由に動けて,いろいろな人に会える立場で地元と関わっているということですよね。
平野 そうです。恐らく今まであればこうした仕事って行政が担うことが多かったのかもしれませんが,僕はフリーランスとしていろんな形で地域に関わる仕事をしています。行政の受託事業として,地元の若者や中小企業を対象にした事業伴走支援みたいな仕事にも関わっていたり,「関門大学」という名前でさまざまな人が学ぶことを通じてつながっていくような取り組みの立ち上げにも関わっています。
下関にはいわゆる中堅企業や個人事業主のような人たちがたくさんいますが,事業としては「なんとなく回っているけど,実は課題がある」みたいな状況が多いなと感じています。でも,そういう人たちって行政の支援も届きにくい。新規創業やスタートアップのような形でもないからこそ,「ちょうどその真ん中」みたいな人たちと一緒に動いていくための仕組みが必要だと思っています。あるいは,地域の若い人たちの中には「何か始めたいけど,何から手をつけたらいいか分からない」という人が多い。そういう人たちとゆるく話す場をつくって,少しずつテーマを深めたり,事業のアイデアを言語化してみたりしています。

僕自身,いまのこの活動を「仕事」と呼んでいいのかは分からないんですけど,正直働いている感覚はあまりないんですよね(笑)。でも,目の前の人たちと話して必要な仕組みを一緒に考えていくというのは,すごく面白いと思っています。
今後は,福岡でも東京でも危機感の強い自治体でもない,中核都市である下関市も自分の活動フィールドとして展開していきますが,ある種中途半端だからこそ,どちらに舵を切るかで,明るい未来が待っているのか,沈み行く船になるのかが変わってくると思います。
個人的にはやはり,学生時代からもずっとテクノロジーに触れてきましたし,人口減少の社会においては,人がやらなくても済む作業についてはどんどんロボットやAIが代替されると思っています。
ロボットやAIなどのテクノロジーは人の仕事を奪うのではなく,本来人がやるべき・やった方がいい場所に時間も労力も頭も割けるようになるというのが本質です。とはいえ,まだまだテクノロジーに懐疑的であったり,活用できていない人や企業が多いのも事実です。人手不足で困る未来が日本全体で見えてるからこそ,中核都市を舞台に「ゆるい・やさしいDX」をどう実装していくかが今後のテーマです。
飛田 今日はとても興味深いお話を伺うことができました。実は私も下関には縁があり,今も親戚が暮らしています。福岡からも近いし,まだまだ下関には知らない魅力もあると思うので,またお話を聞かせてください。今日はありがとうございました。
平野 ありがとうございました。
今回の記事はいかがでしたか?
地域で活動する若者と聞くと「地域を変えたい」という強い意思を想像するかもしれません。けれども,平野さんの歩みから見えてくるのは「地域を変える」ではなく,「地域と関わり続ける」という姿勢です。東京や福岡で得た経験をそのまま持ち込むのではなく,足元を見て対話を重ねる。そして,制度と制度のすき間にある,名前のついていない活動の余白にこそ可能性を見出していく。下関という「知っていたはずの場所」で,あらためて向き合い,関わり直そうとする平野さんの実践は,都市でも地方でも,自分なりの立ち位置を探すすべての人へのヒントになるはずです。
福岡で暮らしていたときにはわからなかった今。異なる場所で暮らすことは自分の培った経験をふりかえる良い機会になると言えるのかもしれませんね。