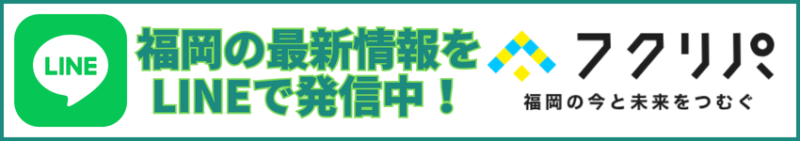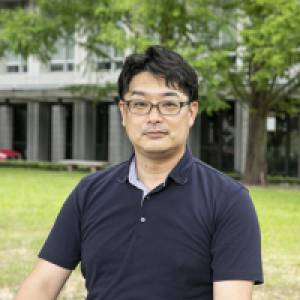近年,福岡市は国内外から”スタートアップ都市”として熱い視線を集めています。2012年に「スタートアップ都市ふくおか」を宣言し,アジアの玄関口という地の利を活かしながら,官民連携で起業支援,スマートシティ構想,アジアの企業や人材との交流強化などを推進してきました。
スタートアップ支援策の充実ぶりは国内屈指。天神ビッグバンをはじめとした都市再開発と併せ,多くの若手起業家が集積する都市へと成長しつつあります。しかし,その一方で福岡のスタートアップ・エコシステムはまだ発展途上にあるのも事実です。事業開発やファイナンスの分野で専門人材が不足していることや,大学で育てた人材が東京や海外に流出してしまうという課題も浮き彫りになっています。
こうした現状に対して,「福岡が“挑戦する都市”として持続的に発展していくためには何が必要なのか」。その問いに鋭く切り込んできた,九州大学ロバート・ファンアントレプレナーシップセンター(QREC)副センター長,五十嵐伸吾氏(通称”いがぽ”)の最終講義が行われました。

今回は,この最終講義の話をもとに,スタートアップ・エコシステムとしての福岡の展望と課題について考えて頂ければ幸いです。
「東京と一緒に沈むのは嫌だった」——いがぽが福岡を選んだ理由
「僕は東京でコミュニティ活動をしていましたが,東京と一緒に沈むのは嫌だった。福岡なら違うやり方ができると思って九州大学に来たんです」
当時,大手銀行でスタートアップ企業(当時は「ベンチャー企業」と呼んでいました)への投資,育成を行う仕事をしていたいがぽが福岡に拠点を移したのは2005年。当時から日本は少子高齢化が加速し,GDP成長も鈍化していることから,まさに「沈みゆく火山島」のような状況だったと彼は表現していたそうです。東京という巨大な都市に集中する経済活動—それは便利で効率的な一方で人口減少社会のリスクが顕在化した際には,真っ先に沈んでしまうのではないかという危機感もあったと言います。

そうした状況の中で教員へのキャリアチェンジ。いがぽはその当時を振り返ってこのように考えたそうです。
「関東圏だけで売上400兆円,福岡はその10分の1。でも,だからこそ福岡にチャンスがあると思った」
東京や大阪,中部圏で日本経済を長らく支えてきた巨大経済圏が沈んでしまう時,そのリスクヘッジとして第三極,第四極が必要ではないか—そんな議論を重ねる中で,彼が選んだのは福岡でした。東京に依存せず,地域独自の挑戦が持続する仕組みを作りたい。その鍵となるのは,教育と地域に根ざしたエコシステムづくりだと確信していたそうです。
実際に,いがぽは福岡を「人と技術の一定の集積が既にある都市」と評価しつつ,だからこそ東京に人材を供給するのではなく,福岡で人が循環する仕組みをつくらなければならないとこれまでも繰り返し語ってきました。
「みんな高いところに避難しようと東京に行く。でも福岡は違う挑戦の仕方ができる場所」。そんな確信が彼にキャリアチェンジに突き動かし,足を西に向かわせるのでした。
シリコンバレー・ボストン・スウェーデンに学ぶ「地域で人材を循環させる仕組み」
いがぽが繰り返し講義で語ったのは,アメリカの2つの都市—シリコンバレーとボストンの事例でした。最終講義の中でもそのことに深く触れていきます。
◇ シリコンバレー:”果樹園”がテック都市に変貌した理由
今でこそ世界のIT企業がひしめくシリコンバレーですが,1950年代までは果樹の栽培が主要産業でした。そんな地域がイノベーションの聖地へと変貌を遂げた背景にあったのは,スタンフォード大学と地域産業の密接な連携でした。
とりわけ重要なのが,”シリコンバレーの父”と呼ばれるターマン教授の存在。ターマン教授は,西海岸にあるスタンフォード大学で育てた学生たちがビジネスの中心地であった東海岸に流出してしまうことに危機感を持ち,地元に優秀な人材を留めるために3つの仕組みを整えました。
1. リサーチパークを整備し,大学発ベンチャーを支援
スタンフォード大学が敷地内にリサーチパークを整備し,学生や研究者が起業しやすい環境を提供。大学発ベンチャーが地域に根付く土壌をつくったこと。
2. 政府や大企業と連携し,地元での研究・雇用機会を創出
国防総省やヒューレット・パッカードと連携し,地元での雇用・研究機会を確保。学生が東海岸に流出せず,地元で挑戦できる仕組みを整備。
3. 卒業生同士が支え合う産業コミュニティを形成
卒業生同士がネットワークを構築し,資金提供やノウハウ共有を実施。失敗しても次の挑戦を後押しする,地域循環型の産業コミュニティを育んだ。
こうした仕組みを整えた結果,ヒューレット・パッカード(HP)やインテルといった企業が次々と誕生し,新陳代謝を繰り返しながら地域に人材と技術が循環する仕組みが生まれました。
◇ ボストン:衰退から再興へ,大学主導の地域変革
ボストンも,かつては製造業衰退で苦しんだ都市でした。造船や繊維といった既存産業が衰退し,経済の停滞と人口流出が進む中,マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心に地域再生への舵を切ったのが1960年代〜70年代のことでした。特徴的なのは,MITがただの教育機関にとどまらず,地域産業や自治体,そしてベンチャーキャピタル(VC)と密接に連携し,新たな産業の担い手としてスタートアップ支援に注力した点です。
いがぽは,こうしたボストンの変化を「大学が産業界と自治体の間に立ち,産業構造そのものを変える役割を果たした好例」と紹介する。そして「既存大企業の支援に頼り続けるのではなく,地域内で挑戦と失敗が繰り返され,新しい産業が自律的に生まれる仕組みを作った」とその本質を説きました。
その上で,自身がいる福岡の現状に話を移していきます。「九州大学で人を育てていても,東京に行っちゃったらどうしようもない」と語り,福岡で育った人材が卒業後に東京や海外へ流出してしまう現状に,いがぽは強い危機感を抱いています。
「東京のための福岡じゃなく,福岡のための福岡にしなきゃいけない」

いがぽは,MITのように地元の大学と地域産業,行政,そして挑戦者たちが一体となり,地元で人材が循環し続ける仕組みこそが福岡に必要だと強調します。挑戦と失敗を許容し,地域の中で再び立ち上がれる土壌づくり—そのために教育機関はどこまで責任を持ち,地域はどう支えるのか。その問いを福岡に投げかけていきます。
◇ スウェーデンに学ぶ「挑戦の前に備える教育」
そして,いがぽが講義の中で特に強調して紹介していたのが,彼自身が長年足を運び続けてきたスウェーデン・ヨーテボリにあるチャルマース工科大学での取り組みです。規模こそ小さいものの,アントレプレナーシップ教育においては世界的な評価を受けている同大学では,他とは一線を画す独自の教育カリキュラムが展開されています。
チャルマースでは,入学から2年間,学生たちは徹底したリスクヘッジ教育を受けます。いがぽは「チャルマースの学生たちは,最初の2年で“失敗の仕方”を叩き込まれる」のだそうです。財務や法務の基礎はもちろん,実際に事業を回しながらどう失敗を乗り越えるか,どんな支援を活用すればリスクを最小限にできるのか,実践的なスキルが徹底的に教え込まれていく。そうした教育を受けた学生たちが起業すれば,その生存確率は85%という驚異的な高さを誇るそうです。ここに彼が進めてきたアントレプレナーシップ教育の心があります。
「僕は,学生に竹槍で戦わせたくないんです」
いがぽはそう強く語りました。挑戦の場を与えることは重要だが,それだけでは意味がない。その前段階で,必要な知識・スキル・ネットワークをきちんと身につけ,自分で“転び方”を学んでおく環境が不可欠だと強調していました。
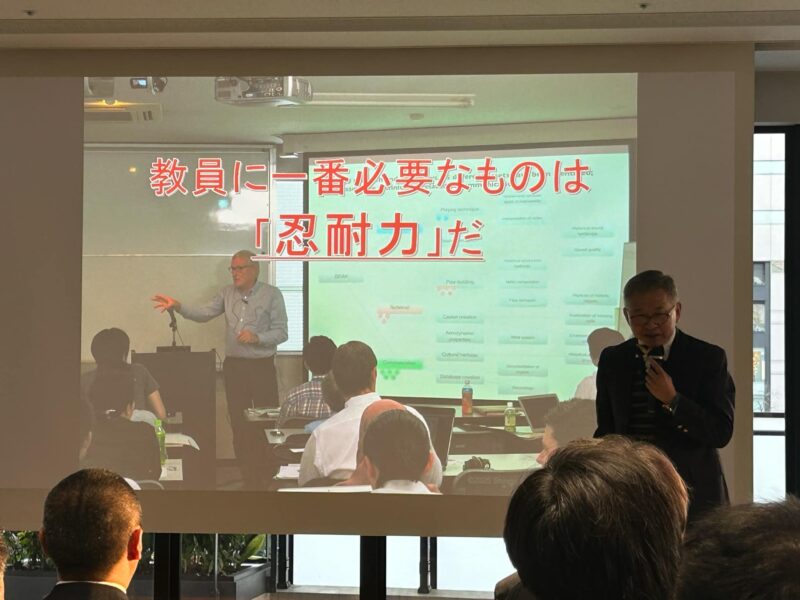
現在,福岡にはスタートアップ支援策が数多く存在しています。しかし,いがぽは「支援策の“数”を増やすことが目的化してはいけない」と講義の中で警鐘を鳴らしていました。大切なのは,表面的な支援の量ではなく,失敗しても再挑戦できる仕組みと,挑戦前に備える教育の“質”をどこまで高められるかにかかっていると。福岡が挑戦者を育てる都市であるために必要なのは,まさにチャルマースのような挑戦前のリスクを抑えつつ,挑戦後の失敗も受け入れる“挑戦者本位の教育と制度”だと力強く訴えかけていました。
===(閑話休題)===
この時点で与えられていた時間はすでに超過。あたふたするいがぽの様子を見て,そのキャラクターをよく知る仲間たちから声がかかります。
「最後なんだから喋りたいだけ喋ったら良い!」(実は私)
ところが,現場を仕切るQRECスタッフの皆さんからはマキのサイン。限られた時間で今日一番伝えたかったメッセージを伝えることになりました。
===(ここまで)===
福岡エコシステムの設計課題——誰が“全体設計”をするのか
いがぽは,福岡のスタートアップ政策を評価しつつ,こう問いかけました。
「福岡で,誰が本気でエコシステムの全体設計をしているのか?」
この10年,福岡はスマートシティ構想やアジアとの連携,スタートアップ支援など多くの先進的施策を進めてきた。しかし,その“部分最適”にとどまってしまっていないか—いがぽはその点に鋭く切り込んでいきます。
「福岡はやれるところからはすぐに動ける。でも,全体を俯瞰して“エコシステム全体としてどう回すか”という視点は,まだまだ足りない」
彼はこのように指摘しました。特に,大学や教育機関で育成した人材が卒業後に関東,関西へ流出してしまう現状には強い危機感を示していました。学生や起業家が福岡で根付き,挑戦と失敗を繰り返しながら再び挑める環境。そのためには,起業初期の支援だけでなく,成長フェーズでの支援や,失敗した後のセーフティネットまで含めた“全体設計”が欠かせない—それがいがぽの問いかけの真意でした。
挑戦し続けられる都市であるために
こうして,最終講義は単なる回顧ではなく,「挑戦する都市・福岡」を目指すために必要な要素を明確に提示して結びに向かっていきます。改めて,福岡を離れるいがぽから最後次のような課題が示されました。
1. 地域に根ざしたアントレプレナーシップ教育の質の向上
いがぽは講義の中で,地域にあったアントレプレナーシップ教育をデザインしなきゃいけないと繰り返し強調しました。全国一律の教育制度ではなく,福岡という地域特性に合った挑戦の場を設計する必要があると。QRECでの実践を例に挙げながら,「地域に根ざした挑戦の機会が,学生たちに“自分ごと”としての社会課題を意識させる」と語っています。また,「教育者は,学生が転びそうな場所がわかっても口や手を出さず,あえて挑戦させなければならない」とも述べ,失敗を許容し再挑戦を促す教育観が重要であると説いています。
2. 成長フェーズ・再挑戦フェーズを支える制度設計
起業初期の支援は福岡にも多く整備されているが,いがぽは「種まきだけで終わらせてはいけない」と指摘しました。「起業後の成長期,そして失敗した後にもう一度挑戦できる仕組みがないと,人は福岡に定着しない」と。具体的には,スタートアップと既存企業の間で人材が流動できること,そして失敗した後の社会的セーフティネットの存在が鍵だと語りました。ここまでの話を受けて,いがぽは「シリコンバレーのように,ベンチャーキャピタルが物理的に近い距離に存在し,すぐに次の挑戦へ進める環境が必要」と言います。事業機会にある福岡に東京からVCや企業が参入してくるのは良いことかもしれないが,本来は福岡からそうした企業を支える仕組みを作り上げることが必要だと。そして,成長支援の不足を課題として挙げていました。
3. 外部から人・資本を呼び込む持続的エコシステム
最後に,いがぽは「東京を見なくていい,もっと外を見よう」と繰り返し語っていましたが,福岡が“挑戦する都市”であり続けるためには単に地元の中だけで完結するのではなく,外部の人材や資本を受け入れ循環させる設計が欠かせないと訴えました。講義ではボストンやMITの例を挙げ,「人材の供給源で終わるのではなく,外から人が集まり定着する仕組みが必要だ」と語りました。行政が東京を意識しすぎるのではなく,アジアや世界市場と接続する柔軟な視点が福岡に求められていると強調していました。
いがぽが福岡に託したもの
いがぽは最後にこう結んで自らの最終講義を終えました。
「僕たちは経験があるから,学生が転びそうな場所がわかる。でも,口や手を出してはいけない。大ケガしない程度に,挑戦させるのを我慢できるかどうかが教育者の役目なんです」

メディアは福岡を“スタートアップ都市”と称えています。しかし未来の福岡が本当に「沈まない都市」であり続けるかどうかは,挑戦し続ける環境が根付くかどうかにかかっています。いがぽが福岡に残した問いかけは,今まさに私たち一人ひとりに向けられています。
最終講義の余韻—次世代へ託されたバトン
最終講義の後には,QRECで学び巣立っていったOBOGと,現役学生たちによるトークセッションも行われました。教員という枠を越え,時に伴走者として,時に一番の挑戦者として向き合ってきたいがぽのもとで学んだ学生たち。その多くが現在,起業家,研究者,地域の実践者として,自らの挑戦を続けています。彼らが語る言葉の端々には,いがぽから学んだ「挑戦し続けることの意味」や「失敗を恐れないマインドセット」が色濃く刻まれていました。

そして夜は,五十嵐伸吾という存在がどれだけ多くの人々を惹きつけ,繋いできたかを物語るような退官記念パーティーが開かれました。福岡のみならず,全国各地から彼に縁のある人々が集まり,場は笑顔とエネルギーに満ち溢れていました。途中,いがぽにまつわるクイズ大会も催され,彼のキャラクターをよく知る仲間たちが次々とユーモアあふれるエピソードを披露し,会場は大きな笑いに包まれました。
いがぽが残した問いかけと挑戦の灯火は,確実に次の世代へと受け継がれていくことでしょう。20年に及ぶ九州大学でのアントレプレナーシップ教育はこれで一旦区切りを迎えますが,まだまだのご活躍を祈念しています。
いがぽへ—挑戦し続ける福岡の未来のために
いがぽ,最終講義,そして長年の福岡での挑戦,本当にお疲れさまでした。私が福岡大学に着任して2年目を迎える頃,QRECではQ-Shop,福岡大学では創業体験プログラムがスタートしていたこともあり,共通の友人であり,良きメンターである村口和孝さんとのつながりで私たちの交流が始まりました。

それから10年と少し。世界トップクラスのアントレプレナーシップ教育研究者との交流,スウェーデンへのツアーとたくさんの学びの機会を頂きました。また,高大連携でのアントレプレナーシップ教育を推進したのは,QRECとは異なる方法で,アントレプレナーシップの種を蒔き,芽吹かせることを試みようとしてきました。

今回の講演では福岡が沈まない都市であり続けるために必要なものは何かという問いかけがありましたが,私は私にできる方法で福岡のみならず,九州をより挑戦しやすい場所にしていくことを自分自身の当座生きる目的にしよう—いがぽの問いかけに対するその答えは,これから形にしていかなければならないことなのだと思います。
「大ケガしない程度に転ばせてくれる教育者であれ」
ロールモデルとして見てきた立場として,失敗を包み隠さず,人懐っこい笑顔で多くの人に愛を語ってきたいがぽが福岡を去るのはとても寂しいです。しかし,いがぽが耕した土壌をより豊かにするために,私もこれからも挑戦を恐れず,次世代を担う人材育成に邁進していきます。
いがぽ,本当にありがとうございました。
そして,これからもどこかでまた一緒に新しい挑戦をしましょう。